ケロイドの手術に関しては一般的に敬遠されることが多く、単に切って縫い合わせだけの方法では、80%以上の高確率で再発し、かえって傷が大きくなってしまうだけ、ということが起こり得ます。
単に切って縫い合わせるだけでは50−100%の確率で再発しますので、Z形成術、W形成術、植皮や皮弁形成術にといったより高度な手術が必要となります。
それらの手技を行なった場合も再発の可能性はありますので、定期的なフォローアップと予防的なステロイドの注射(自費治療)が必要となります。
上記の理由から保険診療での治療では限界があり、当院では自費治療にて手術を行なっています。

オススメの患者様
・事故の跡が気になる
・水ぼうそうの跡
・他院での手術の跡
・他院でのレーザー治療の跡が気になる方
治療を受けられない方
・妊娠中の方
慎重に治療した方がいい方
・授乳中の方
・強迫神経症などの精神疾患をお持ちの患者様
手術により病変を切除し、縫合します。
手術方法は病変、位置により異なりますが、代表的な例を挙げておきます。
■手術直後

■手術後3週間

料 金:1㎝ 107,800円(税込)~
副作用:腫れ、赤み、内出血、縫合不全、感染症、傷が大きくなってしまう場合がございます。
また術後の経過は個人差がございます。
傷の方向をずらすことでケロイド・肥厚性瘢痕の再発を予防します。
またZの形の傷を作ることで傷を目立たなくさせる効果があります。
■手術直後

料 金:1㎝ 107,800円(税込)~
副作用:腫れ、赤み、内出血、縫合不全、感染症、傷が大きくなってしまう場合がございます。
また術後の経過は個人差がございます。
長めの傷に対して適応となります。
Z形成をいくつも作り、Wもしくはジグザグの傷を作ります。傷の張力(つっぱり)を解除するとともに、部位によっては長期的に傷を目立たなくさせる効果があります。胸部のケロイドによく使われます。
■手術直後

■手術後3週間

料 金:1㎝ 107,800円(税込)~
副作用:腫れ、赤み、内出血、縫合不全、感染症、傷が大きくなってしまう場合がございます。
また術後の経過は個人差がございます。
普通に縫い合わせると、傷が引き連れる場合は、V-Y皮弁形成術を行います。近傍の皮膚、皮下組織をずらして三角形の形にして欠損部位を覆います。
そうすることで引き連れ、皮膚のヨレ、歪みをなくします。目の周り、鼻の周りで選択されることが多いです。目や鼻が引き連れたり変形したりするのを避けるためです。
上記は基本的な手技のみですが、患者様に合わせて様々な術式や方法を組み合わせてなるべく傷が目立たないように治療させていただきます。
年間手術実績は※2019年4月~2020年3月の合計7268件でございます。
【内訳:三鷹院2063件・新座院1514件・国分寺院1475件・久我山院840件・志木院1134件・大宮242件】
当法人の理事長である花房火月は皮膚科において低侵襲手術の独自性および術式を広めた実績が認められ、皮膚科医として唯一、The Japan Times紙によりアジアの次世代を担うリーダー100人(100Next-Era Leaders IN ASIA2015-2016)に選出されました。
さらにその3年後には低侵襲手術を広めた功績、および日本におけるシリンジセラピーの普及に貢献したことを評価され世界的な経済新聞紙であるThe New York Times紙に次世代を担うリーダー2019の一人として選出されました。
記事はこちら(https://www.neltimes.com/persons.php/hizuki_hanafusa/)
それ以上 応相談

鼻瘤は酒さ3期とも言われ、原因は完全には解明されていませんが、鼻に皮脂腺の過形成が起こり、鼻が団子鼻になり、変形していく疾患です。皮脂線の閉塞、線維化、血管拡張も起こります。
見た目の問題だけでなく、呼吸しづらいという機能上の問題を引き起こすこともあります。
放置すれば鼻瘤は進行します。
鼻瘤の治療は欧米では一般的ですが日本ではほとんど行われておらず、放置されているのが現状です。当院では他に先駆け鼻瘤の手術を米国より取り入れ、さらに現在はレーザー手術をメインで行なっております。
鼻瘤に対してはこれまでに様々な治療法が考案されています。
代表的なもので
などがありますが他にも様々な機械を使った鼻瘤の手術方法が考案されています。
このうちフラクショナル炭酸ガスレーザー、イソトレチノインは軽症例に限られます。
PDLレーザーは鼻瘤そのものというより、血管拡張の治療に使われます。
実際に鼻が膨らみ、変形してしまった鼻瘤に対しては、メス・電気メス、炭酸ガスレーザー(もしくはEr:YAGレーザー)による除去ということになります。
疾患、治療法の性質上、比較試験を行うことが難しいので、治療の優劣をつけることは難しいのですが、レーザー治療が手術治療よりも安全性、出血量の少なさ、回復の早さに置いて上回っているという報告は散見されます。
しかし逆にレーザー手術も手術療法も大して差がないという報告もあります。
結局のところ、
手術において肝となるのは、皮脂腺の深部のレイヤーを残しながら、過形成した皮脂腺を取り除く、ということになり、どのような術式で行うか、というよりも術者の技量、経験の方がものをいうのでしょう。
経験豊富な術者が症例に合わせ、手術、電気メス、炭酸ガスレーザー治療を使い分ける、もしくは併用することがベストと考えられます。
Schweinzer Kらによると143名の外科的鼻瘤手術を受けた患者のうち70名がアンケートに答えました。そのうち87%が非常に満足、もしくは満足と答え、67%の患者が生活の質が改善したと答えています。38%の患者で再発が見られました。
V. Madanらによると炭酸ガスレーザーにて鼻瘤手術をした124名の患者のうち、118名が素晴らしい結果となり、満足度も高かったと報告しています。
Lazzeri Dらは、鼻瘤に対して外科的手術を行った患者と、炭酸ガスレーザー治療を行なった患者を比較したところ、どちらも優れた結果で、いずれも副作用は軽微であったと報告しております。
当院では炭酸ガスレーザーによる治療を第一選択としてしております。その理由は出血量が減少少ないという報告が多いこと、傷の治りが早いとの報告が挙げられます。
当院では、鼻瘤に対するレーザー手術に力を入れております(一回382,800円(税込))
鼻瘤でお困りの方はぜひ当院にご相談くださいませ。
| 治療前 | 治療後 |
|---|---|
 |
 |
鼻瘤は肥大化し異常に増殖した皮脂腺に他なりません。そのためその余分な皮脂腺を取り除くことが大事なわけですが、それを取りすぎてしまうと瘢痕化(傷跡になってしまうこと)する恐れがあり、皮脂腺を一層残す、ということがポイントとなります。
もし皮脂腺をたくさん残してしまうと効果が不十分となり、取りすぎてしまうと傷跡になってしまうということになりますので、さじ加減が難しい治療法と言えるでしょう。患者様におかれましては鼻瘤の治療の経験豊富な術者を選ぶことをお勧めしたいと思います。
A治療後、傷が治るまでには10−14日程度かかります。それまではガーゼで覆っていただく必要があります。
A局所麻酔の注射には痛みが伴いますが、治療中は、ほとんど痛みはありません。
A鼻瘤の治療法は、メスを使った外科的治療法、電気メスを使った治療、レーザーを使った治療とありますが、本質的にはどれも同じで過形成化した脂腺組織を切除し、下層の脂腺組織を残す、ということに尽きます。データ上はどの治療法も効果、リスクに大差はなく、術者の経験、技量による、というのが本質的なところです。
A主な副作用として瘢痕形成、色素脱失、色素沈着、再発のリスクがあります。
もっとも大きな副作用は瘢痕形成で治療を深く行い過ぎた場合に、起こる副作用です。瘢痕形成を予防するためには、’治療し過ぎない’というが必要でしょう。その点、経験が必要となります。
A欧米のデータですが、鼻瘤治療後、38%の患者で再発が見られたとの報告があります。そのため、当院では半年間の無料フォローアップをさせていただいております。
脂肪腫は、成熟脂肪細胞からなる良性腫瘍で、いわゆる “common disease” ありふれた疾患の一つです。脂肪腫は、皮膚科外来に訪れる皮膚腫瘍の患者様のうち、粉瘤、黒子について多い疾患とも言われています。脂肪腫は、全身どこにでも発症し得ますが、頸部(クビ、特に後頸部)、肩甲部、上腕、背部、大腿など脂肪層に発症します。脂肪組織のあるところに発症することが多いのですが、時に筋肉内、骨膜上や真皮内に発症することもあります。皮下に弾性軟と呼ばれる比較的柔らかい塊として認識されることが多いでしょう。

脂肪腫は上記の通り、発症頻度のとても高い疾患です。脂肪が蓄積しやすい年齢、特に40~60歳台に多く見られます。男女共に頻度が高いのですが、やや男性に多いとされています。
脂肪腫は上記の通り、皮下の脂肪層に見られることが多いです。
皮膚とも下床とも連続していないことが多いのですが、真皮発生型(比較的多い)の場合は皮膚との連続性がありますし、
筋肉内発生型の場合は、下床と連続しているように感じられることがあります。
脂肪腫は痛くも痒くもないため、見えない位置であればなかなか気づき辛い場合もあります。
触るとボコッとした腫瘤を感じることができるでしょう。徐々に大きくなっていき、見ただけでわかるようになる場合もあります。
通常1cm~15cm程度の大きさで医療機関を受診する人が多いようです。
上述の通り緩徐に大きくなっていくことが普通です。
脂肪腫それ自体で健康を害したり、寿命を縮めるようなものではないのですが、あまり大きくなると整容面で問題となったり、運動面での障害となることもあります。
また脂肪腫と似た疾患で悪性の脂肪肉腫との区別が問題となることもありますので、見つかれば切除することが多いです。
弾性軟(脂肪と同様にやわらかい)のことが多いのですが、血管脂肪腫と言う脂肪腫の亜型では圧痛を伴うことがあります。
また、血管脂肪腫はやや硬く感じることが多いです。
1箇所であることが多いのですが、5~8%で多発のことがあります。多発する場合は、上記の血管脂肪腫のことが多いです。
臨床的な亜型としては、
・びまん性脂肪腫症
・良性対側性脂肪腫症
・脂肪腫性母斑
などがあります。
血管脂肪腫も多発傾向という臨床的な特徴があるため、臨床的な亜型と考えることもできます。
2歳以下の乳幼児に発症するまれな疾患で、四肢、躯幹、など全身に脂肪腫が見られるまれな疾患です。皮下脂肪組織のみならず、筋肉内、内臓にも脂肪腫が見られる場合もあります。
頸部を中心に、病名の通り左右対称に脂肪腫が多発する疾患です。頚部、肩部上腕、胸部、腹部、大腿などに左右対称に脂肪腫が見られます。アルコールを多飲する方に多く見られるまれな疾患です。
真皮内になんらかの理由で迷入した脂肪組織より発症する成熟脂肪細胞からなる腫瘍で、皮膚表面にぽこっと盛り上がるように見られ、臀部(お尻)、腰部、大腿部によく見られます。それ程、レアな疾患ではなく、しばしば見られます。
臨床的には古典型と孤発型に分かれ、古典的タイプとしては幼少期より発生する多発集簇する有茎性の病変です。孤発型はドーム状に盛り上がる結節で、大人になってから発症することが多いです。
脂肪腫は臨床的にではなく、病理学的に以下のように分類する方法もあります。
通常の脂肪腫は皮膜の中に成熟した脂肪組織が満たされています。
成熟した脂肪細胞の中に血管成分が多い脂肪腫で多発しやすく、やや固く小型のことも多いです。
成熟した脂肪細胞の中に膠原線維が多く見られるもので、後頚部、上背部などの圧がかかりやすい部位によく見られます。
癒着傾向にあり、切除がやや困難となります。
脂肪腫内に線維芽細胞に似た紡錘型の形の細胞の増殖を伴うもので、その細胞に異形成はなくあくまで良性腫瘍です。
中高年の男性の後首部や肩甲部によく見られます。
脂肪腫内に様々な細胞を含む脂肪腫で、まれです。
その特徴的な外観、および触診で容易に診断は可能です。
ただし悪性腫瘍である脂肪肉腫との鑑別が必要となることもあります。
CTや超音波検査だけでは質的診断までは困難で、MRIによる検査が必要です。
脂肪腫を疑えば手術的に摘出し、病理検査を行うのが現実的でしょう。
もちろんMRIなどの画像診断に容易にアクセスできる環境があればMRIにて事前に診断を行うことが望ましいです。
なるべく傷が小さくなるようにデザインさせていただいております。脂肪腫を摘出する際に、なるべく周囲の組織を傷つけないように素早く手術を行います。脂肪腫が多発している場合も対応させていただいております。
現時点では脂肪腫の治療は、付け薬や飲み薬は無効で外科的に切除するしかありません。
そのため、特殊な場合を除きいかに傷を小さく脂肪腫をとるか、ということが焦点になります。
通常は脂肪腫の直上の皮膚に局所麻酔を行い、皮膚切開を加え下のレイヤーまで慎重に切開を進めていきます。
脂肪腫を同定すると、皮膜に沿って剥離を進め摘出します。
摘出した病変は、その後、真皮縫合、表皮縫合にて閉創し治療終了となります。
・注意点1
真皮より発生している脂肪腫の場合、連続している真皮も同時に切除しないと再発しやすいです。
触診にて皮膚と連続性がある、もしくは超音波検査で皮膚と連続している場合は、その皮膚も含め紡錘形に切除する必要があります。
・注意点2
脂肪腫が房になっている場合がありますので、大きな脂肪腫を一つとって安心しているともう一つ小さな脂肪腫が隠れている可能性があります。
皮膚の流れに沿って切開し、脂肪組織をかき分け、脂肪腫を見つけます。脂肪腫を見つけると、皮膜を適切な層にて剥離し、周囲を傷つけないように脂肪腫を取り出します。きれいに縫合し手術を終了します。
脂肪腫の摘出の際、より傷を小さくするために用いられる方法です。
名前の通り、より小さな切開線から脂肪腫を絞り出す、あるいは揉み出します。
〈 揉み出し法の術式 〉
まず脂肪腫の周囲に原液あるいは希釈した麻酔を注入し、腫瘍を周囲の組織をあらかじめ剥離してきます。
そして最小限の切開を行い、そこからすでに剥離の住んでいる脂肪腫を揉み出す、あるいは絞り出すようにして摘出します。
その後は通常通り、真皮縫合、表皮縫合を行います。
この方法では傷が小さくなり、かつ出血、侵襲が少なくなるのが特徴で、いわゆる低侵襲手術の一つと言ってもいいでしょう。
ただしあくまで従来より傷が小さくなるだけで、傷がなくなるわけではありません。
ただし癒着の強い線維脂肪腫には向かないでしょう。
A現在のところ原因ははっきりしていません。皮膚良性腫瘍は多くの場合、原因不明です。
A脂肪腫があっても日常生活に困らなければ必ずしもとる必要はありません。
しかし、それが脂肪腫であればというのが前提で、脂肪腫ではない他の疾患の可能性もあります。
病理検査なしに、脂肪腫と確定診断することは簡単ではないですので、なるべく切除したほうがいいと考えています。
A症例によって異なるので、なんとも言えないのですが緩徐に大きくなって行くことが多いです。
20cmを超える程大きくなることもあれば数cm程度でとどまる場合もあります。
急速、大きくなるようだとほかの疾患を疑ったほうがいいでしょう。
A脂肪腫自体は悪性化することはないのです。脂肪腫と思われていた物が、実は脂肪肉腫(悪性腫瘍)であったということもあります。
A極端に大きなものや手術が難しい場合を除き、脂肪腫は外来で取ることが可能です。
A例外的な場合を除いて脂肪腫の切除後、翌日より仕事に行くことができます。
小さな脂肪腫の場合は当日から施術に行くことも可能でしょう。
尋常性疣贅(イボ)は高い有病率の割には決定的な治療がなく、本邦においては漫然と液体窒素による冷凍凝固術が行われていることが多いようです。冷凍凝固術は簡便で優れた治療であるのは間違いないが、それ一辺倒では限界があります。足底の固くなったイボなど、冷凍凝固術だけでは到底治らない場合も多々あります。
高い有病率にもかかわらず、イボは治療上の困難をもたらすことが多いです。単独治療は、すべてのケースで完全寛解を達成することはできません。最も一般的な治療法は、冷凍凝固術とサリチル酸 (SA) です。その他、化学物質 (例えば、カンタリジン、ホルムアルデヒド、フェノール)、化学療法(例えば、podofilox、フルオロウラシル、ブレオマイシン硫酸塩)、接触皮膚炎を起こす免疫療法 (例えば、ジニトロクロロベンゼンスクアリン酸ジブチルエステル)と、免疫調節剤 (例えば、インターフェロン、イミキモド)、外科的切除、掻爬(そうは)とレーザー治療などがあります。
疣贅(イボ)の治療の理想的な目的は、損傷を作ることで長期免疫を誘発し、再発なしでイボを除去することです。すなわちイボを破壊するのはなく、免疫を誘導することが大事であるということです。
サリチル酸は、徐々にウイルス感染した表皮を破壊することによって作用する角質溶解剤です。その軽度の刺激は、免疫応答を刺激することがあります。サリチル酸だけで12週間かけて足底疣贅の84%の患者と尖圭コンジローマの67%の患者のクリアランスに成功したとの報告もあります。ただし日本で保険適応のあるサリチル酸は10%程度のものしかなく、疣贅の治療を行うにはじゅぶんな濃さがありません。あくまでその他の治療の補助に止まるでしょう。
液体窒素 (LN2, −196°C) が本邦では最もよく使用される薬剤です。ジメチルエーテル/プロパン混合物 (−57°C) がまたその利便性のために使用されるが、細胞壊死のために十分な組織の温度を誘導する有効性は低いです。冷凍凝固術は、HPV 感染したケラチノサイトの単純な壊死破壊するほか、おそらく効果的な細胞免疫応答を助長する局所炎症を誘発することによってイボの治療に影響を与える可能性があります。
多くの医師は、スプレーを使用するが、綿ウールのスティックは、依然として広く使用されています。これは目の近くや子供や疣贅を治療するときに望ましい場合が多いです。
治療の手技は治療者により異なり、強い場合もあれば弱い場合もあります。
イボの外科的切除は欧米では広く行われており、特に鈍的掻爬、ついで電気メスによる焼灼が多いです。特に顔や手足の糸状疣贅に対して便利かもしれません。ある研究では、65~85%の患者の成功率が報告されています。瘢痕形成は、これらの治療の後によく見られ注意が必要です。再発も多く最大で30%の患者様に再発が見られます。足底の瘢痕化はこの治療で最も大きな副作用です。
銀硝酸の繰り返しの日常使用を伴う化学焼灼は、イボのクリアランスを有効ですが、時折、色素性の傷跡が発生することがあります。70名患者を対象となるプラセボ対照研究では、9日間で硝酸銀の治療を行なった群では3回行うことで、43%のイボの寛解と26%のイボで改善を見られ、プラセボに比べ有効な治療であることがわかりました(プラセボ群で11%の寛解と14%の改善が見られました。)
ご存知の通り、様々なレーザー治療が、イボ治療のために検討されています。二酸化炭素 (CO2)レーザー、エルビウム: ヤグレーザー(Er:yag)、パルス色素(PDL)、およびNd:yagレーザーが含まれます。
●二酸化炭素レーザー(炭酸ガスレーザー、CO2レーザーと同義)
CO2レーザーは、イボの最初のレーザー治療として最初に行われ、1980年代から使用されています。水によって吸収される10600 nmの赤外線の波長が照射することで治療を行います。CO2レーザーは2つのメカニズムによって疣贅を治療します。まず、レーザービームはイボの血管を焼灼します。2番目に、ビームが、HPV感染が感染している表皮の層を蒸発させます。2つの論文でCO2レーザーによるイボの治療を行なった所、12ヶ月で 64~71%の人の疣贅の治癒したと報告されています。しかし、術後の痛みや瘢痕形成といったリスクがあります。
●パルス色素レーザー
パルス色素レーザー(PDL)は、ヘモグロビン吸収ピークと一致する585から595 nm の波長を発します。PDLは、疣贅に栄養を供給するために作られた拡張した毛細血管を破壊します。これによってウイルス分子の宿主である表皮細胞を飢えさせるという仮説があります。更に、PDL はウイルスの熱に敏感な固有の結果として、HPV ウイルス自体を破壊することが示唆されています。
●Nd:YAGレーザー
仮定されているNd:yagのイボ治療におけるメカニズムはPDLレーザーに似ています。Nd:yagレーザーは、1064 nm の波長を放出し、ヘモグロビンのターゲット800nmと1100 nmの間に適度な吸収ピーク、疣贅の拡張した真皮血管の凝固と破壊を行うことでイボの感染している細胞を飢えさせることでイボを除去していう説があります。メラニン色素を含むイボであれば、メラニン色素に反応し、イボの感染した細胞自体を破壊するという機序もあります。
●Er:yagレーザー
そのEr:yagレーザーは2940 nmの波長を発し、10600-nmのCO2レーザーに比べて10倍以上の水に対する選択性であります 。したがって、Er:yagレーザーが、熱損傷を最小限に抑えながら、組織を蒸発します。イボの治療におけるメカニズムは、正常の組織が視覚化されるまで、一層ごとに病変の表皮を直接焼灼します。
他のレーザー治療機に関しても、イボ治療の治験が行われています。Yangらホルミウム: YAGレーザー (波長、2140 nm の;)を使用し、顔面疣贅を持つ42名の患者を治療し、すべての疣贅を1セッション後にクリアしました。(顔のイボは治りやすいことを考慮する必要があります)。副作用は軽度であり、軽度の萎縮性瘢痕(7%)と色素の変化(14%)が見られましたが、6ヶ月後のフォローアップで改善されました。532-nm カリウムチタニルリン酸 (KTP) レーザーもイボ治療で検討されています。
●光線力学的療法(フォトダイナミックセラピー)
この処置は、イボの感染した細胞にアミノlaevulinic酸 (ALA)のような光吸収性の化学薬品を吸収させることにより決まります。レーザーまたは非レーザー光をターゲットとなる組織に照射することで、光酸化させ損傷させます。20%のALAもしくはプラセボ(偽薬)クリームのいずれかの適用後の589-700nmレーザーの3回の治療を受けた45名の患者において、ALAを用いレーザーを照射された群では4ヶ月の後に疣贅のクリアランスやイボのサイズの減少の大幅な改善を生み出したことを示しました。
●ホルムアルデヒド
ホルムアルデヒドは殺ウイルス活性また、0.7% ゲルまたは3%の溶液として海外で使用されることがあります。通常のイボ治療法と組み合わせることでウイルス疣贅のクリアランスを早める可能性があります。足底疣贅を持つ200人の子供は6〜8週に3%ホルムアルデヒド溶液で使って、疣贅の80%のクリアランスが見られました。
●グルタルアルデヒド
グルタルアルデヒドは、海外では10%の溶液またはゲルとして利用可能であり、ホルムアルデヒドのようにそれは皮膚を硬化させ、そのほかの治療とのコンビネーションが容易になります。20%のソリューションを使用して非対照試験では、3ヶ月、毎日一回で25人の患者の72%で、疣贅を完治させました。この処置では、皮膚の色素沈着のリスクがあります。また20% グルタルアルデヒドの使用により皮膚壊死の報告がありました。
●ポドフィリン・ポドフィロトキシン
ポドフィリン、ポドフィロトキシンの混合物内の有効成分、抗細胞分裂薬(抗有糸分裂薬)として機能します。肛門性器部の疣贅の治療で使用されることが多いです。治療が有効である可能性があるが、激しい炎症、無菌膿疱形成と二次感染の危険性があります。日本では販売されていません。
●ブレオマイシン
イボ病巣内に細胞毒性物質ブレオマイシンを注入する方法は他の治療法で失敗した疣贅を治療するために使用されています。研究では、250-1000U/mLのブレオマイシンの濃度を使用しています。これより濃度が高くても効果は高くならないことがわかっています。ブレオマイシンの使用で31%〜100%の応答率が報告されています。治療中、治療後の痛みは主な制限要因です。結果となる壊死は、瘢痕化、色素の変化と爪の損傷を引き起こす可能性があります。局所麻酔が必要になることが多いです。ブレオマイシンは、通常の注射器を使って注入されることができます。そのほか、入れ墨器具を改造したもの、真皮への多穿刺注射、または単にブレオマイシン一滴を垂らしてから微小な針で繰り返しイボをチクチクする方法などが考案されています。62名の患者を対象として非対照研究は、毎月の治療により、平均して4ヶ月後には、92%の患者に成功率を示しました。ブレオマイシンの病巣内注射後に有意な全身性吸収が報告されていますので、妊娠中の女性で使用すべきではありません。
●レチノイド(ビタミンA誘導体)
レチノイドは、ニキビ治療、小じわ治療などでよく用いられるクリームですがイボの治療にも用いられます。0.05% トレチノインクリームを用いた25人の子供のイボを対象として無作為化対照試験は、25人のプラセボ群の32%と比較して、トレチノインを使用した群では85%の完治率を示しました。レチノイドの内服がイボ治療に効果的であるとの報告も数例あります。
●局所感作
イボにかぶれ物質を塗布することで、免疫を誘導することでイボを治療します。かぶれ(遅延過敏症)の誘発は、イボの治療として使用されています。ジニトロクロロベンゼンそしてスクアリン酸ジブチルを使用されているが、ほとんどの研究は、diphencypronの効果を研究していました。2つの大規模なオープン研究は、diphencyproneの有望な結果を示しています。一つでは、diphencypronは、8週間で134名の患者に毎週使用され、60%の応答率となりました。別のレトロスペクティブ研究では、平均して3週間ごとに治療した48人の患者の88%は14週間の間に顕著に改善が見られました。この治療の欠点は、厄介な湿疹反応がある一方で、一部の患者では効果がないという点です。
●シメチジン
シメチジンは、元々は胃薬として使われている薬ですが理由不明の免疫効果があり、疣贅を治療するための使用が提唱されています。いくつかのオープントライアルは、有効性を示唆したが、対照試験はプラセボ以上の利点を示しませんでした。
当院では患者様の症状に合わせて治療を行いますが、1~2週に一度の冷凍凝固術を基本とし、改善がなければ炭酸ガスレーザーを行うという方針としております。
メラノサイトは、皮膚の色素産生細胞であり、通常、表皮内に表皮真皮接合部と毛包内で存在します。いくつかの良性の腫瘍は、メラノサイトから派生しており、典型的には個々の遺伝子変異の結果です。母斑細胞母斑、色素性母斑、ホクロは本コラムでは同義とします。
多くの大人はホクロを持っているが、その数は個人差があり、一人当たりわずか数個から何百個にも至ります。母斑は出生時にも稀に存在し、先天性母斑として知られています。むしろ、ほとんどのホクロは、通常出生後二十年の間に形成されます。どんな人であれ、合計のホクロの数は20代の間にピークと考えられ、このピークはいくつかの既存のホクロの臨床退行(一般的に30歳後半でホクロは徐々に退行していく)と新しい母斑の形成の減少の組み合わせによるものです。ホクロの臨床的退行は、完全に理解されていない過程であり、その間ホクロが縮小し、完全に消え、加齢に伴ってホクロ退行の頻度が高くなります。
ホクロは、他の潜在的な前癌病変と比較して、比較的若い頃に発生します。対照的に、光線性角化症は、皮膚扁平上皮癌の前駆体であることがあり、40歳では先立って珍しく、80歳代と90歳代でも、加齢に伴って非常に流行します。ホクロは、20歳代に主に発生し、年齢が進むと少なくなるが、理由は不明のままです。わずか数母斑をもつ者がいる一方で、数百母斑ある者がいる理由はよく理解されていません。量の面では、遺伝的な原因と紫外線と他の環境変異原性の組み合わせは、役割を果たす可能性があります。
母斑細胞母斑(ホクロ)は、最も見られるサイズは2〜6ミリメートルであり、臨床的に均一な色をしており、対称性を持っています。
病理学的には以下のように3つのグループに分類されます。
ホクロがどうしてこれらの3つのタイプがあるのか?どのようにして異なるタイプが形成されるのか?ということは、よく理解されていません。他の良性メラノサイト系母斑もあるので注意が必要で、青色母斑、太田母斑、スピッツ母斑、クラーク母斑などがあります。ただし、内容が膨大になりすぎるため、この記事では詳細には説明しません。
病理学的には、母斑細胞母斑は限局的、対称的である母斑細胞の巣で構成され、単調で際立った変化は少なく母斑細胞母斑の2つの基本的な病理組織学的特徴は巣形成(ネスティング)および成熟です。ネスティングは、組織内の細胞の小さな房を形成する母斑細胞の傾向を指します。成熟は、母斑の特徴であり、巣の構造と母斑細胞診で (浅から深) 徐々に進歩的な変化を指します。病変に深くなると、巣のサイズが減少し、細胞や核体量が減少し、色素の生産が減少し、細胞の形状の変化が発生します。
成熟に関する細胞学的特徴は、3つのグループに個々の母斑細胞を分類するために用いられ、タイプA、BとCがあります。タイプA母斑細胞は、正常の表皮メラノサイトの形態と最も類似しており、表皮と真皮上層といった母斑の最も表面的な部分の巣でよく見られます。タイプ B 母斑細胞は、比較的小さな巣の真皮中層でよく見られ、また、比較的サイズが小さく、形は丸いです。タイプ C メラノサイトは、主に真皮下層の部分に個々の細胞として発見され、紡錘形です。母斑細胞母斑で観察される複雑な構造は、細胞の内因性と外因性の両方が組み合わさり母斑を形成を作り、制御不能の成長を防ぎ、恒常性を維持することを示唆します。メラノーマでは、組織化されたネスティングと成熟は失われる傾向があります。ネスティングまたは成熟が、組織内の腫瘍抑制の相互作用を反映していることが示唆されるが、はっきりしたことは不明です。
メラノサイト母斑の悪性形質転換について述べると、2つの遺伝子が重要です。NRAS と BRAF-V600E と呼ばれる遺伝子は、悪性細胞への変換に重要な役割を果たしています。これから下記詳細を述べます。
NRAS 遺伝子は、主に細胞分裂を調節するために関与している N-Ras と呼ばれるタンパク質を作るための指示をしています。シグナル伝達と呼ばれるプロセスを通して、タンパク質は細胞外から細胞の核に信号を中継します。これらの信号は、成長し、分裂 (増殖) または成熟し、特殊な機能 (差別化) を取るために細胞に指示します。N-Ras タンパク質はGTPase であり、これがGTPを GDP に変換するということです。N-Ras タンパク質は、スイッチの様に動作し、それは GTP と GDP の分子によってオンとオフになっています。信号を送信するには、GTP の分子に (結合) を付けることによって、N-Ras タンパク質をオンにする必要があります。N-Ras タンパク質が、GTP を GDP に変換する時には、オフになっています (不活化)。タンパク質が GDP に結合されている場合、それは細胞の核に信号を中継しません。NRAS 遺伝子は、癌遺伝子として知られているクラスに属しています。変異すると、癌遺伝子は正常な細胞が癌になる可能性があります。
BRAF 遺伝子における特異的な変異 (変化) は、細胞内のシグナルの送信や細胞増殖に関与するタンパク質を作ります。このBRAF遺伝子変異は、悪性黒色腫や大腸癌を含むいくつかの種類の癌で発見されることがあります。がん細胞の増殖や広がりを増す可能性があります。腫瘍組織のこのBRAF変異検査は癌の新しい治療を計画するのを役に立っているのかもしれません。
欧米では一般的にクラーク母斑がメラノーマに進展しやすいとされています。クラーク母斑そのものは日本人でも非常によく見られるタイプのホクロです。そのクラーク母斑がメラノーマへ変化する病因の仮説は、通常の母斑細胞からメラノーマに変化することにより発生します。この仮説では、典型的な母斑細胞⇨異形成母斑⇒メラノーマ細胞に変化し、最終的に侵襲性メラノーマの形成すると考えられます。そして、遺伝子的の変化の進行蓄積によって駆動される経路と考えられています。一方向に段階的に進行していくという説明はメラノーマの発生の一部を説明しているにすぎず、多くの研究データではほとんどのメラノーマで、進行がより複雑であることを示唆し、発癌ヒット(発癌に必要な遺伝子の損傷、変異)の複雑な組み合わせによって母斑細胞がメラノーマになりうる多くの異なるパースが含まれています。
通常の母斑細胞から黒色腫への従来の進行は線形方法で描写されてきました (一方向に段階的に)。しかし、個々の病変で、ある特定の段階を飛ばすか、または全く起こらないかもしれません(非線形進行経路)。個々の病変のすべての段階を通る直線的な進行は、おそらくかなり珍しいです。BrafV600E突然変異を起こしたメラノサイトは通常の母斑細胞を生みます。NRASとBraf V600E突然変異が起こるメラノサイトは、より一般的に(ホクロを経由せずに)新たにメラノーマを形成します。メラノーマ のおよそ2/3は、よく知られている良性前駆体病因を発症せず、おそらくメラノサイトのMAPK経路の突然変異の発生からなります。分裂促進因子活性化したプロテインキナーゼ(MAPKs)は、増殖、分化、運動、ストレス応答、アポトーシス、生存といった種々の基本的な細胞プロセスに関与する、セリン/スレオニンプロテインキナーゼ群です。
母斑の大半は、メラノーマに進行することはありません。 多くは、生涯にわたって臨床的に安定したままになります。一方、退行するものもあり、 (デッドエンド経路)いくつかよくある母斑は、後で異形成母斑を生むかもしれないが、これはおそらくかなり珍しいです。異形成母斑が、よくあるホクロよりもメラノーマにより進行しやすいかははっきりしていません。
稀にホクロはメラノーマを生じさせるが、大多数のホクロはメラノーマには決してなりません。推定では、ホクロの悪性化率は、40歳未満の200,000 人に1人以下から60歳以上の男性の33,000人におよそ1人です。生涯にわたってメラノーマに任意の個々の母斑の進行のリスクは、男性は3,000人に約1人であり、女性は11,000人に1人です(筆者注:日本人ではもっと少ないであろう)。このような理由からホクロの予防的除去はそれほど一般的でありません。しかし、母斑の進行をスクリーニングし、ダーマスコピーで検査することは、メラノーマの同定と早期治療に大いに意味があります。
ホクロが癌化するリスクはかなり低いがない訳ではありません。ホクロが極端に大きい場合や、ホクロがたくさんある場合、様子が変わってきた場合は必ず専門医に相談するようにしましょう。
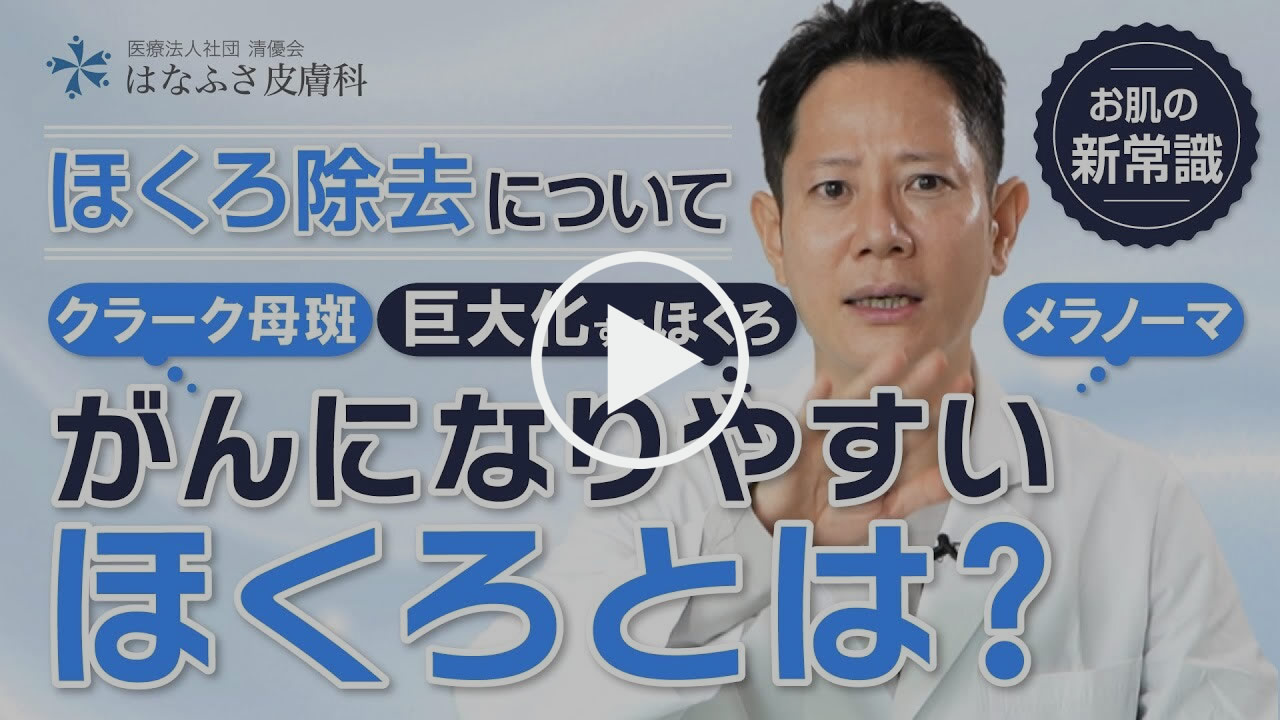
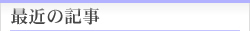

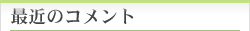

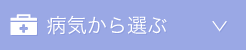
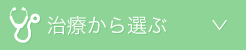
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。