日本皮膚科学会誌に掌蹠膿疱症の統計学的な検討が掲載されています(札幌医科大学皮膚科、加瀬先生ら)
その統計を見ますと、掌蹠膿疱症の患者様のうち、皮膚科的な治療で症状が完全消失した方(著効)、もしくは過角化や落屑は残るものの、紅斑、水疱、膿疱は消失し再燃のない方(有効)の合計が41.2%でとあります。著効、有効は患者様にとっては「治った」と実感できる改善度と思われます。
何度かブログで触れさせていただきましたが、掌蹠膿疱症の発症には喫煙が関与しているといわれており、禁煙により症状の改善が見込めるとされています。
本論文では、喫煙を継続中の患者様では、著効、有効が39.1%であったのに対し、禁煙中と禁煙歴なしの患者様では著効、有効が51.5%であったと書かれています。
実際このデータからだと、禁煙がどの程度、皮疹の改善に役立つのかは、はっきりとはわかりません。治療開始と同時に禁煙を行った患者様の著効、有効率が分かれば、もっと禁煙による治療効果への影響を知りえたのではないか思います。今回のデータの39.1%と51.5%では思ったほど大きな差が無いように感じるのですが、もしその方法で、統計を取ったなら、もっとはっきりした差が出たのではないかと感じます。
ふけが気になるというお問い合わせが増えていますのでお答えしたいと思います。
ふけをきたす疾患は
湿疹
脂漏性湿疹
接触皮膚炎(かぶれ)
アトピー性皮膚炎
などの湿疹群
尋常性乾癬
などの炎症性角化症
頭部白癬
などの真菌症
が代表的かと思われますが、ふけを訴えてご来院される方の多くは、湿疹、もしくは脂漏性湿疹の方です。
頭部湿疹と頭部脂漏性湿疹の違いですが、頭部脂漏性皮膚炎は男性に多く、生え際多く、境界明瞭(どこからどこまでが病変部かはっきりしている)で、痒みが少ないのが特徴です。
それに対して湿疹は、性差はなく、境界が不明瞭で痒みが強いのが特徴です。
原因としては、脂漏性皮膚炎はMalassezia furfurという菌が関与しているという説がありますが、感染症と考えるのではなく、あくまで湿疹の一種と考えていただきたいと思います。Malassezia furfurが補体と呼ばれる免疫物質を活性化させるため、皮膚炎が増悪するとも言われています。治療はステロイドの外用薬や、Malassezia furfurの増殖を抑える抗真菌薬の外用を行います。
湿疹の原因としては、シャンプーの洗い残しやすすぎ残しや、シャンプーのときに爪を立てて擦ることにより頭皮が傷みシャンプーそのものの刺激を受けること、頭を洗わないために不潔になってしまうこと、ヘルメットや帽子などで頭皮が蒸れた時間が長時間続きさらに摩擦が加わること、髪の毛が非常に豊かで頭皮が常に蒸れていて外からの刺激に弱くなっていること、寝ているときに枕と擦れること、など様々です。特に気を付けていただきたいのが、ふけがあるからと言って、ごしごしと爪を立てて頭を洗うことです。そうすれば頭皮が痛み外からの刺激を受けやすくなったり、表皮細胞からサイトカインが放出されることで湿疹は必ずと言っていいほど増悪します。シャンプーをしっかり泡立ててから、指の腹で優しく頭皮を洗っていただきたいと思います。
春~夏であれば、若い方や汗のかきやすい方は毎日、そうでない方は2日に1回程度の洗髪が望ましいと考えています。
気温が上昇し、少し汗ばむこともある季節となりました。
この時期に紫外線の増加、花粉症皮膚炎とともに注意していただきたいのが、汗のかき始めによる痒み、湿疹です。
適度に汗をかくと、角質に水分が供給され、乾燥肌の予防になりますし、皮膚の温度が上がり過ぎるのを防いでくれ、さらに汗に含まれる抗菌ペプチドと呼ばれる成分が、皮膚に細菌が増殖するのを防いでくれたりもします。汗をかくこと自体は皮膚にとっていいことの方が多いと思われますが、通常、アトピーの患者様などは、汗をかくと皮膚がかゆくなるため、汗をかかないようにされている方も多いと思われます。学校で体育の後にシャワー浴を導入すると、アトピーの患者様の症状がよくなったとのデータもあり、逆に汗が皮膚にとどまったままにしていると、皮膚炎が悪くなるという考えもあります。
では、汗は皮膚にとっていいのか悪いのか、ややこしくなってきますが、私はシンプルに、健康な皮膚とっては汗は健康な状態の維持に役立つが、湿疹や乾燥のため角質が傷んでいる皮膚にとっては痒みの原因になると考えるのがいいと思います。
つまり汗をかくこと自体は誰にとってもいいことなのですが、それは角質の状態をある程度整えてからのほうがいいということになります。
長引いた冬の乾燥やそれにともなう痒み、擦過によって、角質が傷んでいる方はたくさんおられます。そのような方が急に汗をかき始めると痒みが増悪し、湿疹に至ってしまうかもしれません。汗のかき始めの季節ほど、きちんと保湿し、角質の状態を整えることをお勧めしたいと思います。
帯状疱疹の患者様が増えているようです。
帯状疱疹について詳しく知りたい方は
https://mitakahifu.com/zoster/
を御参照ください。
帯状疱疹は、後根神経節(神経の奥深く)に潜伏している水ぼうそうウイルスが何らかのきっかけに再活性化することにより発症します。極端な疲労や、慢性的なストレス、大病などが誘因となることがありますが、最近、帯状疱疹の患者様が多数、ご来院され、帯状疱疹が増えているのかもしれないという印象を持っております(偶然かもしれません)。
帯状疱疹は、水ぼうそうと正反対の流行パターンを示すことが知られています。同じウイルスが原因なのになぜ?と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、その理由を簡単に紹介しておきます。水ぼうそうは空気感染する疾患ですので、水ぼうそうが流行している間は、多くの人が水ぼうそうウイルスと接する機会が多く、それがいわば自然の予防接種の役割をし、帯状疱疹の発症が抑えられるからだと考えられてるのです。帯状疱疹は、後根神経節に閉じ込められている水ぼうそうウイルスに対する監視機能(抗体)が甘くなることにより発症するのですが、普段から水ぼうそうウイルスと接していると監視が厳しくなり、帯状疱疹の予防になる、ということのようです。
皮膚科医や皮膚科ナースは普段から水ぼうそうウイルスと接する機会が多いため帯状疱疹になりにくいという説も聞いたことがあります。
本日は日本小児皮膚科学会雑誌からです。尾内一信先生による「難治化する皮膚感染症とその対策」を参考にさせていただきました。
当院にご来院していただいた患者様で、とびひや、皮下膿瘍、化膿性爪囲炎などの皮膚感染症の患者様は、初診時に綿棒のようなもので、傷口を擦ってその綿棒を検査に提出された、という経験がある方が多いのではないでしょうか?
それは傷口についている菌の種類と、どのような抗生剤が効き易いのかを調べているのです。検査結果が返ってくるまでに1週間程度かかり、その間にすでに病気が治っていることがほとんどなので、「その検査は本当に必要なのか?」と思われる方も多いかもしれません。しかしわたしは、皮膚感染症の患者様は基本的には細菌検査は必要と考えております。というのも最近は細菌が抗生剤が効きにくくなっていることが多く、細菌検査を行っていない場合には、最初に投与した抗生剤が効かなかった場合、次にどの抗生剤を使えばいいか分からなくなってしまうからです。
最近は特に黄色ブドウ球菌のうち、様々な抗生剤が効きにくいMRSAという菌が大きな問題となっております。MRSAで毒性の強いものが増えているという報告もあります。とびひの原因菌のうち、MRSAが占める割合は日本の平均で、26.9%とされており、東京都では26.3%と書かれています。
私自身きちんと統計を取ったわけではないので、はっきりしたことは申し上げられませんが、三鷹では26.3%よりは低い印象がありますが、やはりそれなりの確率でMRSAが検出されるのは間違いありません。MRSAが原因菌の場合は抗生剤が効きにくいことが多く、細菌検査の結果を見て、抗生剤を選んでいく他ないということになります。
なぜこれほどまでにMRSAが増えたかというと、やはり抗生剤の使いすぎのせいだ、と指摘されています。ある抗生剤をたくさん使いすぎると、その抗生剤に抵抗性をもつ細菌が増える傾向にあります。今後、画期的な抗生剤が開発される見込みは低く、今ある抗生剤を大事に使っていこうという風潮になっており、私も不必要な抗生剤の投与は大いに慎もうと考えております。
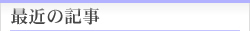

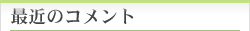

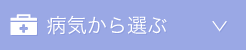
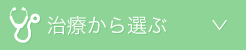
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。