The American Society of Colon and Rectal Surgeons’ Clinical Practice Guidelines for the Management
of Pilonidal Disease
アメリカの大腸直腸外科医学会による毛巣洞に治療ガイドラインについて紹介します。
●剃毛、レーザー脱毛 グレード1C(強く推奨する。質の低いエビデンスあり。)
膿瘍を形成していない毛巣洞に対しては殿裂部(お尻の割れ目)の毛を剃ることや術後に週一回程度剃毛したり、レーザー脱毛を行うことで、再発を抑制することができる。
まあその通りですね。他院で手術だけされて、剃毛がされていない症例を見たことがありますが、術後1ヶ月程度でまたムダ毛が皮膚の中に侵入しようとしていきている所見がみられたこともあります。
せっかく毛巣洞の手術を行っても、その傷が治っている最中からすでに再発の原因が見られてきているということになります。
毛巣洞の治療において剃毛、レーザー脱毛は重要です。部位が部位なので自身で剃毛することは困難なので、クリニックでレーザー脱毛を行うことをオススメしたいと思います。
●フェノール法(膿疱のない毛巣洞に対して)グレード1B (強く推奨する。中程度のエビデンスあり。)
陥入爪の手術法として有名なフェノール法ですが、海外では毛巣洞の治療法としても有名です。
まず剃毛し、病変を掻爬しその後、フェノールにて腐食させ、シストや瘻孔を壊し、癒着させます。
治癒率は65ー100%で、再発も20%以下であったとされています。
本法ではあまり行われていない治療法ですが、優れた治療法ですので、フェノール法になれたクリニックでは取り入れてもいいでしょう。
●フィブリン毛のり グレード2A(弱く推奨する。良質の根拠があり。)
慢性の毛巣洞の手術中にフィブリンのりを使用してデッドスペースを埋めるという方法はそれなりに再発や術後の合併症を減らすことが示唆されています。
ただし、保険適応の関係で日本ではほんとど使われておらず、今後も使われる可能性は低いでしょう。
●膿瘍を伴う急性の毛巣洞の患者にてしては切開排膿を行う。グレード1B(強く推奨する。中程度のエビデンスあり。)
初回の急性毛巣洞に対しては切開排膿だけで60%ー85%の確率で完治させることができると示されています。
ここでいう切開排膿は日本で行われている切開排膿とはかなり意味合いが違っており、米国ではかなりきつめに切開し、中の膿を完全にとりのぞき、周囲を掻爬し、上皮成分や肉芽、瘻孔をきちんと取り切ることを指します。これらをきちんと行えばほぼ再発することはありません。
ここで言及されている切開排膿は日本で行われている様な腫れている部位に少しメスを入れて膿だけ抜き取る手技とは根本的に異なります。ちなみに日本で行われている最初に少し膿だけ抜きとり少し落ち着いたところで切除、単純縫合する、という方法は再発率が高いのではないか、という論文が多数あります。個人的には日本型の毛巣洞の標準治療は時間がかかる上に、患者様の苦痛も長引き、再発率も高く、ほぼメリットがないと感じております。世界では術式も進化してきています。
●慢性の毛巣洞の患者には切除術を行う。グレード1B(強く推奨する。中程度のエビデンスあり。)
慢性毛巣洞に対して切除術を行うのは当然としても、いろいろな治療法があります。
単純に切除縫合する方法もありますし、切除し縫合しない方法、皮弁を形成し縫合部を殿裂部からずらす方法があります。・
日本では単純に切除縫合する方法という最も簡単が行われていますが、これは簡単であるというだけがメリットで、再発率が極めて高い方法です。論文によっては65%に及ぶ再発が報告されています。そのため、個人的にはほとんど行うことがありません。
単純縫合するくらいなら、縫合せずにオープン法とした方が優れています。そのほうがはるかに再発が少ないことがわかっています。
ただ病変が大きすぎてオープン法にできない場合や、即社会復帰が必要でオープン法が困難な場合は皮弁形成術を行い、縫合ラインを殿裂部からずらすといいでしょう。この方法は術者に多少経験がないと難しいというディメリットがあります。
●複雑で再発性の毛巣洞に対しては皮弁形成術を行う。グレード1B(強く推奨する。中程度のエビデンスあり。)
病変が進行している場合は、単に切除縫合するだけでは不十分で、広めに切除し、皮弁形成術にて閉創する必要があります。LimbergフラップやKarydakis フラップが代表的です。
●内視鏡を使った低侵襲手術を急性、もしくは慢性の毛巣洞に行う。グレード2B(弱く推奨する。中程度のエビデンスあり。)
内視鏡を使い瘻孔より挿入し、瘻孔やシストを焼灼して行く方法です。再発も少なく社会復帰も素早行くできていい方法なのですが、特殊な装置が必要なことと、保険適応がないことから今後も日本で普及して行く可能性は低いと思われます。
当院では熟練した形成外科医もしくは皮膚科医が最適な治療をご案内させていただきます。
もし毛巣洞でお困りの患者様がおられましたらぜひ当院にご相談くださいませ。
新年あけましておめでとうございます。
昨年はコロナ禍の1年となりましたが
はなふさ皮膚科にご来院いただきまして誠にありがとうございました。
新しき年、皆様のご要望により一層お応えできるよう医師・スタッフ一丸となり
さらに精励してまいります。本年もご厚誼のほどお願い申し上げます。
医療法人社団清優会 はなふさ皮膚科
明けましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりありがとうございました。
旧年中は三鷹院移転、拡張などに伴い、患者さまに御迷惑をおかけすることも多かったと思いますが、大きなトラブルもなく1年を過ごせましたことを大変ありがたく思っております。
本年も患者さまのため、スタッフ一丸となり全力を尽くす所存です。
より多くの方の皮膚の健康のために貢献できればと思います。
皆様のご健康を心よりお祈りしております。
今年も何卒よろしくお願い申し上げます。
1/18(土)橋本医師は12:30までとなります。
日本における皮膚腫瘍切除に関する功績を評価され、Next Era Leader’sとしてトロフィーをいただきました。


今月末に表彰式を予定されていましたが香港のデモに伴う影響で中止になってしまいました。
残念ですが仕方ありません。香港に平和が訪れることを心よりお祈りしております。
さて、私が初めてジャパンタイムズ紙より表彰されてから4年の歳月が流れました。たった4年しか経っていないのか、、、というのが率直な感想です。4年前はまだ皮膚科における低侵襲手術(傷を小さくすることを目指した治療)が珍しく、毎日のように全国より皮膚腫瘍でお困りの患者様が来られている、という状況でした。
当時は皮膚科での低侵襲手術はリスクが高すぎる、病理診断がおろそかになる、といった理由で色々とバッシングも受けたりしました。
それでも全国より切実な悩みを抱えた患者様がご来院されていたので、「皮膚科における低侵襲手術は必要なものだ」という信念は揺るぎませんでした。
その後、低侵襲手術を売りにするクリニックが瞬く間に増えていきました。
たった4年で低侵襲手術がメンストリームとなるとは想像すらしていなかったです。
しかしこの4年で低侵襲手術が主流になる一方で、やはり危惧していた問題が生じてきたのも事実です。診断があやふやになるという問題です。
中には切除した検体を検査せずに捨ててしまう、というクリニックもあると聞いております。
たとえ肉眼的には粉瘤であっても、病理検査の結果、癌であった、などという例も稀ではありますが存在します。
手軽さだけを売りとして、きちんと病理検査も行わないクリニックは言語道断と言っていいでしょう。
低侵襲手術をやるからには正確な術前診断、そして術後の病理検査が欠かせません。
今後、そのようなことがないようにきちんとした情報を伝えて広めていかないといけないという風に考えています。
まだまだやるべきことはたくさんあります。気を引き締めて頑張っていきたいと思います。
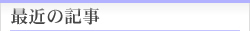

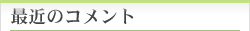

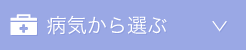
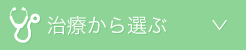
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。