冬に多い病気、というよりは冬(寒さ)に特徴的な病気、といえばいいのでしょうか?あまりにも有名な病気のため問い合わせが非常に多いのですが、それほど頻度は高くない病気です。
寒い日に外に出て風に吹き付けられた際、露出部に蕁麻疹が出てかゆくなる。
冬の寒い日にジョギングをして汗をかいて、そのままにしていたら蕁麻疹が出た。
冷たい水で手を洗ったり食器を洗ったりすると、手に蕁麻疹が出てかゆくなる。
アイスクリームなどの冷たいものを食べたら、唇が脹れてかゆくなる。
といった症状が典型的です。
症状に気がつかないうちに冷たいプールで泳いでショック症状を起こすこともありますので注意が必要です。
なるべく寒冷刺激を避けることが重要となります。通常の蕁麻疹同様、抗ヒスタミン薬、抗アレルギー薬の内服も効果があります。
中高年の方の寒冷蕁麻疹には、クリオグロブリン血症や骨髄腫、リンパ腫、白血病などが隠れている場合がありますので、精密検査をお勧めする場合があります。
とはいえ、それほど頻度の高い病気ではなく、検査をしてみると普通の蕁麻疹であったり手湿疹であったりすることがほとんどなのです。しかし本当に寒冷蕁麻疹であった場合、症状に気がつかないと、急激な寒冷刺激を全身に受けた場合、重篤な症状を引き起こすことがありますので、注意が必要な病気といえると思います。
暑い夏が終わり、秋らしい天気の日が増えてきました。初秋に多い疾患を少し羅列しておきたいと思います。
①毛虫皮膚炎 チャドクガの毛虫は秋にも大量に発生し、その毛によるかぶれが増えております。毛虫に直接接触しなくても、毛虫が大量にいる木の下を通っただけでも毛虫の毛が風で運ばれて毛虫皮膚炎を発症することがあります。
対策:なるべく毛虫のいるところは避けるようにしましょう。チャドクガの毛虫はツバキ科の植物を好むとされています。
②花粉症皮膚炎 初秋も、ブタクサやヨモギなどの花粉による皮膚症状の増悪がみられることがあります。
対策:花粉症皮膚炎のある方が、なるべく肌を露出しないようにし、家に帰ってきたら顔や手を水ですすぐようにしてください。
③ダニの死骸によるアトピー性皮膚炎の増悪 夏に増えたダニの死骸などによりアトピー性皮膚炎が増悪するケースがみられます。
対策:部屋に掃除機をこまめにかけ、なるべく雑巾で床を拭いていただきたいと思います。布団をよく干し、シーツもまめに変えるようにしてください。絨毯やラグなどで不要なものは捨てた方がいいとされております。
④乾燥肌、皮脂欠乏性湿疹 湿度が徐々に下がりだし、乾燥肌やそれによる痒み、湿疹の患者様が増えています。
対策:入浴後しっかり保湿するようにしていただきたいと存じます。不必要に肌を擦らないようにするのもポイントです。
女性型脱毛症という脱毛症があります。
頭頂部を中心に広く薄毛がみられ、男性のように完全に毛髪が消失するわけではないのですが、一本一本の毛が細く短くなります。徐々に進行していきます。頭部全体が薄くなるわけではなく、後頭部の毛髪はしっかり保たれているのが、大きな特徴です。
以前は、男性ホルモンが関与している脱毛症である男性型脱毛症(AGA)と本質的には同じものと、と考えられていましたが、近年ではAGAの特効薬であるプロペシアが無効なことなどから、別の病気であると考えられています。数年前までは女性の男性型脱毛、などと呼ばれておりました。
現時点でも女性型脱毛の原因ははっきりしていません。
患者様の数は増えてきているようです。
女性型脱毛が疑われた場合、ホルモン検査を御希望される患者様が多いのですが、特定のホルモンの異常によって女性型脱毛が発症しているわけではないですので、基本的には診断にホルモン検査は必要ないと考えております。
1~2%のミノキシジル外用薬などにて治療を行います。
光脱毛やレーザー脱毛の後に、少し時間をおいてかえって毛が濃くなる現象のことを硬毛化現象と呼びます。特に珍しいことではなく、二の腕、背中、肩、うなじなどの毛を脱毛した場合は、かなり高頻度でこの現象が起こります。光脱毛を行った場合は、部位によって硬毛化現象は10~50%の確率で起こるの報告もあります。
そもそも、光脱毛やレーザー脱毛は、毛穴にエネルギーを当て、毛根を破壊することでむだ毛を生えてこないようにする方法ですが、完全に破壊できない場合は、その機能を活性化し、かえって毛が濃くなってしまうようです。(組織をあえて損傷することで、新たに再生を促し活性化させるという意味ではケミカルピーリングや、フラクショナル炭酸ガスレーザーの理論に通じるものがあるかもしれません)
当院でも、硬毛化しやすいとわかっている部位に関しては異なる波長のレーザーを二種類使い分けるといった工夫を行い、十分な対策を行っております。もし硬毛化してしまってもNd:YAGレーザーを高出力で照射するといった工夫をすることで脱毛することが可能なので、お困りの方はご相談いただきたいと存じます。
とびひの患者様が急増しております。
昨日一日だけでも30名近いとびひの患者様がご来院されました。
とびひは水疱性膿痂疹と非水疱性膿痂疹に分かれますが、いずれも患者様も、起炎菌のほとんどは黄色ブドウ球菌です。(非水疱性膿痂疹は溶連菌を起炎菌とすることが多いとする説もありますが、本邦の他の報告同様、当院でも起炎菌はほとんど黄色ブドウ球菌です)。
黄色ブドウ球菌のうち、大部分の抗生剤がきかないMRSAという菌が有名で特に注意が必要ですが、今のところMRSAを検出することはそれほど多くはありません。ただし、とびひになる前に、夏風邪などで抗生剤を長く飲んでいた、というお子様では、MRSAを検出する可能性が高くなっております。おそらく抗生剤を飲んでいるうちに、鼻腔や表皮に常在する黄色ブドウ球菌が耐性化するのでしょう。やはり不用意な抗生剤の使用は慎まなければなりません。
現時点では、とびひのオーソドックスな治療
①まずはセフェム系抗生剤の内服と、ニューキノロン系外用薬(もしくはステロイド外用薬)による治療を行う。
②効かない場合は内服薬を、ホスホマイシンという抗生剤に切り替える。
で効かなかった患者様はおらず、治療に難渋することはほとんどないのですが、今後も耐性菌には十分注意していくつもりです。
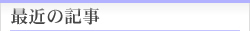

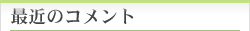

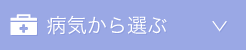
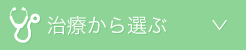
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。