本日は私の誕生日でしたが、診療、テレビの取材、皮膚科学の調べごとなど行っていると11時近くになってしまいました。
さすがにこの年になると誕生日が特別な日、という感覚はなくなりますが、また1年平穏に年を重ねられたことはありがたいことと感じております。両親やお世話になった方に感謝したいと思います。
次の一年は今までやってきたことを形として残せるように頑張りたいと思います。
これからもよろしくお願いいたします。
掌蹠膿疱症は、手のひらと足の裏に無菌性の膿疱がたくさんできる病気です。
現時点では明確な病因は分かっていませんが、細菌性の口蓋扁桃炎や歯周病などの病巣が原因ではないかと考えられていることがあります。また掌蹠膿疱症の患者様の多くが喫煙者であることが知られています。口腔内の金属アレルギーが原因で発症することもあるとされています。
欧米では乾癬の一亜型として扱われていますが、本邦では乾癬とは別の疾患として扱われていることが多いようです。
私は以前から掌蹠膿疱症に強い関心を抱いております。というのも、病巣感染や金属アレルギーが原因のことがあるのに、なぜ手のひらと足の裏にしか皮膚病変が出ないのか?という点です。病巣感染(たとえば溶連菌)に伴って、リンパ球が刺激され、交差反応によって皮膚を攻撃するとしても、全身に病変が出ずに、掌蹠にのみ病変が出るのは理解できません。掌蹠の皮膚としての特殊性について検討する必要があるように思いますが、あまりそれについての検討はなされてないようです。(私の推測では、掌蹠膿疱症で角質下膿疱を形成するにはある一定の時間が必要であり、それ以外の部位では角質下膿疱を形成する前に、角質が脱落してしまうのだろうと思います。逆に言えば膿疱を形成されるまでに比較的長い時間が必要な経路が関与しているのだろうという推論が成り立ちます。)
そのほか喫煙がどのような機序で同疾患の発症に関与しているのか、なぜビオチンが効く方、効かない方がいらっしゃらるのか、なぜ日本と世界とは取り扱いが異なるのかなど、そのほかにも疑問点はたくさんあります。
いずれそれらの疑問点についての私の推論を述べたいと思います。
稗粒腫は非常に一般的な皮膚疾患でお困りの方も多いと思います。
目の周りによくできる、小さなくりっとした白い皮膚腫瘍です。
稗粒腫(=milia)で検索しするとたくさんの画像が出てきますので、参考にしていただければと存じます。
http://www.google.co.jp/search?q=milia&rls=com.microsoft:ja:IE-SearchBox&oe=UTF-8&rlz=1I7ADFA_ja&redir_esc=&um=1&ie=UTF-8&hl=ja&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=PBDWTs6aDMLtmAXVwfVR&biw=1024&bih=496&sei=QxDWTqnQFuLumAWfupz7Dg
自然に発生することもありますが、欧米の教科書には目の周りを習慣的に擦ることが原因で発症することもあると記載されていますので注意されたほうがいいかもしれません。
治療法ですが、注射針の先で刺して内容物を取り出す治療が一般的ですが、それだけだとすぐに再発しまいますので、当院では内容物を取り出した後に炭酸ガスレーザーで照射を加える方法をとっています。
非常に簡単な治療ですので、もしお困りの方がいらっしゃればご相談いただければと存じます。
尋常性魚鱗癬(じんじょうせいぎょりんせん)という皮膚がカサカサする疾患があります。有病率は250人に1人とそれほど珍しい疾患ではないのですが、ご存知の方が非常に少ない疾患のようですのでご紹介しておきます。
尋常性魚鱗癬は常染色体優性遺伝形式をとり、ご両親のうち、どちらかがこの疾患をお持ちなら、男女問わず50%の確率でお子様に遺伝します。
1~4歳ころから四肢や背側の皮膚がカサカサしだし、少し厚くなった鱗屑(ふけ)が魚のうろこのように見えなくもないため、魚鱗癬という病名がついています。ただの乾燥肌とどう違うのか?と思われる方もおられると思いますが、確かに区別が難しく、見落とされていることが多いと思われます。例えば1日100人の患者様が来られる皮膚科クリニックでは単純計算でも3日にお1人は尋常性魚鱗癬の患者様が来られるはずであります。さらに皮膚科に来られる集団は、そうでない方の集団よりも尋常性魚鱗癬の患者様が多く含まれているはずであり、2日に1人、もしくは1日に1人、尋常性魚鱗癬の方を診察してもおかしくないはずです。
しかし現実的には尋常性魚鱗癬と診断される方がかなり少ないのは、やはり診断の難しさにあるのではないかと考えております。
診断のポイントは遺伝形式と、膝窩や肘窩などの関節屈側部には病変がみられない点です。そういうと非常に診断が簡単そうに見えますが、現実にはそれほど簡単ではなく、尋常性魚鱗癬の患者様が乾燥性の湿疹やアトピー性皮膚炎を合併した場合は、関節屈側部にも病変がみられるようになり、そうなれば通常の小児乾燥性湿疹や、アトピー性皮膚炎との鑑別は困難を極めるようになります。
尋常性魚鱗癬の患者様のうち約半数の方はアトピー性皮膚を合併すると報告されていますが、逆にアトピー性皮膚炎の患者様のうち尋常性魚鱗癬の合併率は3~30%と報告されているようです。3~30%というのは非常に幅のある数字であり、すこし言葉が悪いのですが、まともな数値とは言い難いように感じます。
このことが間接的にどれほど尋常性魚鱗癬の診断が難しいかを物語っています。つまりアトピー性皮膚炎の患者様を拝診した場合、皮膚がカサカサしていることが多いのですが、それが魚鱗癬によるものなのか、皮脂腺が未熟なためなのか、軽度の湿疹に伴って二次的に乾燥が目立つのか、区別することは容易ではないということを示しています。
しかし鑑別のポイントはいくつかあり、例えば、軽度の湿疹に伴って二次的に乾燥が目立つ方の場合は、湿疹を治せば、乾燥もなくなるという点などがあげられます。
尋常性白斑はシミとは逆に、皮膚の色が白く抜けてしまう後天性の疾患で、皮膚科外来ではしばしば見かける疾患です。皮膚の色が白く抜けている部位を白斑と呼びます。
整容的な問題により、患者様にとってしばしば精神的なストレスとなります。
徐々に白斑が広がることもあります。手のひら、足の裏をのぞき、全身どこにでも発症しえます。
なぜ尋常性白斑が発症するのか、についてはこれでもかというほどたくさんの説が提唱されています。
①自己免疫説・・・抗体、もしくはT細胞が色素細胞を攻撃してしまうという説。
②色素細胞自己破壊説・・・色素を産生するときに作られる中間代謝物に毒性があり、それをうまく処理できなくなったために色素細胞が破壊されてしまうという説。
③神経説・・・尋常性白斑が神経節に沿って発現することがあるため、神経線維が発症になんらかの関与をしているのではないか?との説。
④活性酸素説・・・皮膚における代謝障害により活性酵素が増加し、色素細胞を傷つけることにより発症しているのではないか、という説。
どれが正解なのかはなかなか難しく、これ以上の考察は今回は割愛したいと思います。
難治性皮膚疾患の代表とされ、「治らない」と思っていらっしゃる方も多いと思います。
現状ではステロイド外用のみで経過を見られていることが多いのですが、確かにそれだけだと治療成績は高いとは言えません。やはり光線治療も併用するほうが良く、それを併用した場合、かなりの確率で良好な色素再生が見られるという実感を持っております。
論文的にも半数以上の方で良好な色素再生が見られたとの報告が多数あり、決してあきらめてしまう疾患ではないと思っております。
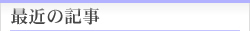

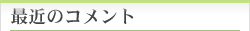

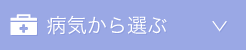
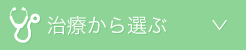
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。