また日本皮膚科学会誌からです。
汎発性皮膚そう痒症とは、全身に(=汎発性)、皮膚病変がないにもかかわらず痒みが生じる疾患のことで、二次的に湿疹ができることもあります。
湿疹があるから痒いのではなく、痒くて掻くから湿疹に至ってしまう点が普通の湿疹と異なります。例えば、透析中の患者様は特に湿疹がなくともシビアな皮膚のかゆみに悩まされる方が多く、皮膚の乾燥、内因性オピオイド(モルヒネ類似物質)、皮膚の神経伝達異常、甲状腺異常などが原因とされています。
本ガイドラインは、以前に書いた慢性痒疹ガイドラインhttps://mitakahifu.com/prurigo2/
https://mitakahifu.com/prurigo1/
と重なるところが多いので、詳細は割愛しますが、本ガイドラインでもやはり推奨度Bは保湿だけであり、抗ヒスタミン薬の内服はC1、ステロイド外用はC2でしかないという点です。痒みを訴える患者様は、ステロイド外用薬が処方されることが多いと思いますが、ステロイド外用薬は抗炎症薬であり、炎症を伴わない痒みに対しては当然無効であるということを我々医師は十分認識しながら診療を行わなければなりません。
紫外線治療に関してはエビデンスレベルが比較的高く、Broadband UVBが推奨度BでNarrowband UVBがC1です。Narrowband UVBは治療効果が高く、副作用の少ない狭い範囲の波長の紫外線のみを照射する治療法ですが、Narrowband UVBではなく、Broadband UVBがきくということは、現時点ではわかっていない波長の紫外線が有効ということが示唆され、その波長を特定する必要があると思います。
週末はある抗ヒスタミン薬の発売記念講演会に参加してまいりました。
ヒスタミンは花粉症や蕁麻疹の発症、アトピー性皮膚炎などの痒みにおける最重要物質の一つであり、ヒスタミンの遊離を抑えることで症状を改善することができます。それを目的としたのが抗ヒスタミン薬と呼ばれる薬で、非常に多くの種類があります。
その中で、どのような基準で薬を選んでいけばいいか、という点を簡単に述べておきたいと思います。
まず第一選択としては、鎮静作用の少ない(眠くなりにくい)第二世代と呼ばれる薬剤の中から選びます。第二世代の中でも特に鎮静作用の少なく、効果が強いものが好まれる傾向にあります(鎮静作用が強い≠効果が強いということはすでに証明されています)。
内服方法は毎食後3回飲むもの、朝夕食後2回飲むもの、夕食後、もしくは就寝前に1回飲むものがあり、大まかに言って効果が同じであれば、1回で済むものの方が優れていると言えると思います。
さらに血中濃度が上がってくるまでに必要な時間があり、それが短いほど効果が素早く、一刻も早く症状を抑えたい場合は、より早く血中濃度が立ち上がってくる薬剤を選択する必要があります。
そして、代謝経路が腎代謝がメインのもの、肝代謝がメインのものがあり、腎障害、肝障害のある方であれば、代謝経路を考えてご処方しなければなりません。
さらに、第二世代抗ヒスタミン薬は、抗ヒスタミン作用以外にも、さまざまな抗アレルギー作用があり、それは薬剤によって若干異なってきますので、症状や抗ヒスタミン薬の内服歴を考慮し、薬を選択するようにしています。
慢性痒疹診療ガイドラインについての続きです。
今回は主に治療についてです。内科的な基礎疾患から慢性痒疹が発症している可能性が高い場合は、基礎疾患の治療が最優先されるのは言うまでもありませんが、まずはアトピー性皮膚炎などと同様にスキンケア、生活指導を行い、ステロイド外用を行うように推奨されています。
ステロイド外用は、推奨度B(行うように勧められる)となっておりおます。ただ慢性痒疹はなかなかスキンケアとステロイド外用だけでは良くならない症例が多いのが特徴で、その場合にどうすればいいか?というのが最大の問題であります。
その他の治療についての推奨度ですが、
推奨度C1(行うことを推奨してもいいが、十分な科学的根拠はない)
・ステロイド局所注射、ステロイド内服、亜鉛華軟膏重層
・抗ヒスタミン薬の内服
・液体窒素療法
・活性型ビタミンD3外用薬
・鎮痒性外用薬(オイラックスなど)
・紫外線療法
・免疫抑制薬外用(プロトピックなど)、内服(ネオーラルなど)
・カプサイシン軟膏外用
・保湿剤外用
・漢方薬内服
推奨度C2(科学的根拠がないので、勧められない)
・抗生剤内服、抗不安薬内服
推奨度C1~C2(適応を絞ればC1ということなのでしょうか?)
・サリドマイド内服
・ナリフラフィン塩酸塩(レミッチ)内服
となっております。つまりほとんどの治療は横並びに、十分な科学的根拠がないということになります。そうすれば、副作用少なく、保険適応のものから順番に試していくしかない、ということになり、ややガイドラインとしては味気ない印象をうけてしまいます。それだけ難しい疾患ということもできると思いますが。。。
推奨度C1~C2といったあいまいな推奨度を作るくらいでしたら、もう少し症例を詳しく分類し、例えば、70歳以上の方で、慢性痒疹を患って3年以上経過している方に対しては、○○治療は推奨度Bというようにしたほうが、臨床には役に立つようにも感じられます。
当院では、スキンケアの徹底(擦らない、掻かない、洗いすぎない、刺激の強い洋服を着ない、部屋を乾燥させない等)、ステロイド外用、保湿剤の塗布を原則とし、抗ヒスタミン薬も2週間ほど試していただき、効けば継続としていただいています。
それでもあまりよくならない方がいらっしゃるのも事実で、その場合は、紫外線治療や液体窒素療法などを行っております。紫外線療法の一つであるナローバンドUVBはクリニックに頻繁に通える方であれば、かなり効く印象を持っております。液体窒素療法は、結節性痒疹の数の少ない方であれば、有効なように感じます。逆に結節性痒疹の数の多い患者様には液体窒素療法は苦痛が大きいだけであまり効かない印象を持っております。もともと体力があり、恰幅のいい方には、漢方薬の黄連解毒湯が著効する場合もあります。掻きむしって眠れないという患者様には短期間、抗不安薬や睡眠導入薬をご処方することもあります。
今月の日本皮膚科学会雑誌に慢性痒疹診療ガイドラインが掲載されていますので紹介させていただきたいと思います。
同ガイドラインでは、慢性痒疹を結節性痒疹と多形慢性痒疹に分類しております。当院でもたくさんの結節性痒疹、多形慢性痒疹の患者様がご来院されています。
同ガイドラインでは、「掻痒が特に強い例、皮疹が広範囲に及ぶ例、治療に抵抗性がある例、きわめて難治で慢性に経過する例では、内科的疾患から皮疹が出ている可能性を考え、全身検索を勧める、詳細な問診、適切な血液検査、画像検査などを行う」と明記されております。
これまでは治療抵抗性でかつ重度の慢性痒疹の患者様に対しては全身検索を行う、というのが標準的と考えられていたように思うのですが、それから一歩進んで、重度の慢性痒疹の患者様には、初めから全身検索を行うように推奨されています。
高尿酸血症、糖尿病、甲状腺異常、血液疾患、腎肝機能障害などに伴い慢性痒疹が出現することは有名事実なのですが、どのタイミングで採血を行うかは、かなり微妙なところで、私も悩むことが多かったのです。今後は、重度の慢性痒疹の患者様は、初診時から採血をする必要があるかもしれません。健康診断のデータをお持ちなら、持ってきていただいたほうが便利だと思います。
治療については、後日紹介したいと思います。
ストレスがホルモンや白血球の機能に影響を与え、皮膚に影響を与えるということは以前ブログでも紹介しました。しかし臨床的に最も問題になるのはストレスに伴う擦過行動かも知れません。
ストレス下に置かれていると些細な痒みが気になったりします。私も勤務医時代に当直時に蚊に刺されただけでまともに眠れなくなった経験があります。当直時というストレス下において蚊に刺された程度の痒みでもすごく気になってしまいます。また暇な時間に少しでも眠らなければいけないというプレッシャーのもとでは、睡眠を妨げる痒みがイライラの原因になってしまい、激しく掻いてしまいます。掻いてしまえば表皮細胞からたくさんのサイトカイン(炎症細胞を呼び寄せるなどの機能を持つ伝達物質)が放出され、また神経からサブスタンスP(肥満細胞などに作用し、ヒスタミンなどの痒み物質の遊離を促す)が放出されることにより、痒みが一層ひどくなってしまいます。また掻くことで、角質が痛み、さらに外からの刺激を受けやすくなってしまいます。結果、痒みが増し、イライラの原因になって、さらに掻いてしまうしまうという悪循環に至ってしまいます。そして、ゆっくり寝ることができなければ、翌日さらにストレスが増してしまいます。私もその当直の翌日薬を付けられるまでの間に何度も掻いてしました。
このような状況はそれほど特殊なものでもなく、かなり多くの患者様が同様のストレスと痒みの伴う皮膚疾患(慢性湿疹、アトピー性皮膚炎、結節性痒疹、慢性単純性苔癬)の悪循環に悩まれているようです。その場合は、すこしでもゆっくりとお休みできるように、軽い睡眠導入剤などを短期間処方されていただくと、症状が著効することがあります。
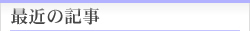

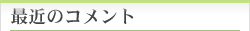

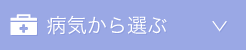
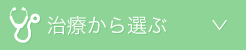
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。