アトピー性皮膚炎の患者様に血液検査でTARCという値を1ヶ月に一度検査することが認められております。TARC値はアトピー性皮膚炎の病勢を反映し、先月よりTARC値が下がっていればアトピー性皮膚炎の病勢は低下していると言えますし、逆にTARC値が上がっていればアトピー性皮膚炎の病勢は上がっているということになります。
私も初めてこの検査のことを知ったときは、「アトピー性皮膚炎の病勢は痒みと、湿疹の範囲などを診れば分かるのに、どうして採血が必要なのか?」と思われるかもしれません。しかしよく調べてみると、TARC値が上がっている患者様は、一見症状が落ち着いているようでも、アトピー性皮膚炎を再燃してしまう可能性が高く、逆にTARC値が下がっている患者様は、一見症状が悪化しているようでも落ち着いてくる可能性が高いということが分かります。
アトピー性皮膚炎の症状は日々変化し、診察日のポイントで症状をとらえても本当の病勢をとらえているとは限りません。たまたま診察日は調子が良かった、などということは良くあることです。
TARCを測定することで、本当の病勢を評価出来る可能性が高いため、当院でもこの検査を取り入れ有効活用しております。「本当に良くなっているか分からなくて治療のモチベーションが上がらない」、というような患者様に特にお勧めしたい検査方法です。
ステロイド外用薬を小さな子どもに使うのは心配、という親御さんのご意見を時々いただくのでお答えしたいと思います。
通常、一時的や湿疹やかぶれ、虫さされの場合は、ステロイド外用薬の使用は1〜2週間でとどまりますので、強さを極端に間違えない限り、副作用は出ようが無く、小さなお子様に使っていただいても全く問題ないと思います。
実際のところ、ステロイド外用薬の副作用で問題になるのは、長期に使わなければ行けない場合、つまりアトピー性皮膚炎の場合、ということになります。
強力なステロイド外用薬を小さなお子様に長期(数ヶ月から数年)で使った場合、皮膚が薄くなったり、ニキビが出来たり、色素が薄くなったり、むだ毛が濃くなったり、皮膚カンジダ症にかかったり、といった副作用が出る可能性があります。
逆に全く使わなかった場合は、アトピー性皮膚炎がひどくなり、湿疹を搔き壊しているうちにとびひになったり、アトピーマーチが進行し、喘息、アレルギー性鼻炎、アレルギー性結膜炎などを併発しやすくなります。目の周りをかきむしっているうちに白内障になることもあります。さらに、痒くて眠れず発育障害、学習障害を招くことさえあります。
では、ステロイドを含まない抗炎症外用薬(NSAIDS外用薬)はどうかというと、長期で使った場合、かえってかぶれの原因となることがあり、アトピー性皮膚炎の患者様に使うことはあまりお勧めできません。
タクロリムス外用薬という、ステロイドを含まない外用薬もありますが、傷のあるところには使えませんので、搔き壊しの傷のある患者様には使えません。また2歳以上でないと使えないという制限もあります。
では、どうすれば良いかといいますと、やはりステロイド外用薬を使用しなければいけないと考えております。副作用を避けるためには、適切な強さのステロイド外用薬を短期間使い、湿疹をしっかり押さえ込むことが大事です。当院では、最初の2週間にしっかりとステロイド外用薬で湿疹、痒みをしっかり押さえ込み、その間に生活環境を整えていただいたり、しっかり保湿する習慣を付けていただくことで、アトピー性皮膚炎を再燃しにくいようにご指導させていただいております。その後は症状が再燃したときのみ少量のステロイド外用薬(2歳以上のお子様の場合、タクロリムス外用薬)を使用する、という方針にしております。それで今のところ目立った副作用も無く、良好な治療成績を得られていると考えています。
アトピー性皮膚炎の患者様で、なかなか良くならずに困っている患者様も多いかと思いますが、我々の経験上、そういった場合にチェックすべき項目を網羅的にまとめたので、もし良ければご活用していただきたいと存じます。
アトピー性皮膚炎患者様チェックリスト
□使うべき外用薬の量はご存じですか?1fingertip unitを是非覚えて下さい(外用薬をチューブから人差し指の先端~第一関節までの長さを出したものが、1fingertip unit=約0.5gです。その量が大人の手のひら2個分の面積の皮膚につける量に相当します)。
□痒みが良くなるとすぐに付け薬をやめてしまっていないですか?ざらざら、ごわごわした感じがなくなり、肌がなめらかになるところまで、薬をつけて下さい。
□薬がなくなってから皮膚科に行っていませんか?定期的に皮膚科に通うようにしましょう(増悪期2週間に1度程度、安定期1ヶ月に1度程度)。薬がなくなって症状が悪化し、我慢できなくなってから皮膚科を受診される方も多いのですが、それではいつまでたっても良くなりません。
□完全には良くならないとあきらめていませんか?アトピー皮膚炎は基本的には、ほぼ完治に近い状態を維持できる疾患です。
□湿疹が治っても保湿剤の外用を続けてください。
□肌に直接接触する物はなるべくコットンの物を使って下さい。
□入浴時、皮膚をこすっていないですか?石けんを泡立てて、手で優しく洗うのが正しい洗い方です。ナイロンタオルは使わないで下さい。入浴後も、優しくタオルで水滴を拭き取るようにしましょう。
□湿疹部も石鹸で洗いましょう(夏場は、1日1回、冬場は、1日~3日に1回)。湿疹部は石鹸をつけてはいけないと考えている方もおられますが、それは誤りです。
□石けん、シャンプー、リンスのすすぎ残しはないですか?
□化粧品を変えてから湿疹が出来やすくなった、ということはないですか?
□しみる化粧品を使い続けていないですか?
□皮膚が乾燥していないですか?夏場もエアコンで空気が乾燥し、乾燥肌になってしまうことがあります。乾燥が気になる方は保湿剤を使うようにしましょう。
□汗をかいたらすぐに拭き取るようにしましょう。下着の替えを持って行くといいかもしれません。
□汗をかいた場合、なるべくすぐにシャワーを浴びましょう。
□寝ているときに汗びっしょりになっていませんか?適度に通気性のいい部屋でお休み下さい。
□枕カバーやシーツはまめに取り替えるようにしましょう。
□枕や布団はまめに干すようにしましょう。
□部屋はまめに掃除をするようにしましょう。掃除機をかけた後に、雑巾がけもした方が望ましいです。
□絨毯やラグ、ぬいぐるみはなるべく捨てるようにしてください。
□睡眠不足になっていないですか?
□過度のストレスはないですか?
□食生活が乱れていませんか?(コンビニのお弁当、ファーストフード、スナック菓子はなるべく避けるようにしましょう)。
□(小児の患者様の場合)食物アレルギーはないですか?
□ペットの毛が原因になっている可能性はないですか?
□無意識のうちに皮膚をかいていないですか?皮膚をかくことが癖になっていませんか?
□爪を短く切りましょう。
□間違ったむだ毛の処理の方法をしていませんか?カミソリや、除毛クリームは皮膚の負担になります。
昨日、「かゆみ治療のUP TO DATE2012」という勉強会に参加してきました。
京都府立医科大学の加藤教授の講演会が参考になりました。
アトピー性皮膚炎の治療は痒みがよくなったからと言って、ステロイドやタクロリムス軟膏の使用を止めてはいけない、肌がつるつるになるまで続けなくてはいけないと、当院でもよくご説明させていただいていますが、その根拠を述べられておりました。
まずアトピーの湿疹部というのは、皮膚に過剰に免疫反応が起こり、主にリンパ球が集まってきて炎症が起こっている状態ですが、ステロイド外用薬を付けると、リンパ球が冬眠状態になります。その時点で痒みがなくなるため患者様はステロイド外用薬をやめてしまうことが多いのですが、それではまた何かの契機にすぐにリンパ球が目覚めてしまい、湿疹が再燃してしまいます。そのため「ステロイドは効かない」という実感を持ってしまわれる方も多いと思われます。そこからステロイドをさらに一週間くらい続けると、リンパ球がアポトーシス(自滅)し、湿疹が再燃しにくくなりいます。そこまでステロイドの外用を続けなければならないというわけです。
もちろんステロイドの外用を長期間続ければ皮膚が薄くなったり一時的に皮膚免疫が低下するといった副作用がありますが、保湿剤を併用し、湿疹が治った後も1ヶ月程度保湿剤にてスキンケアを続ければ、皮膚は回復します。
アレルギーの原因になりやすい物質があることがわかっていますが、なぜアレルギーになりやすい物質があるのかについては、恥ずかしながらあまり意識したことがなかったのですが、面白い文献があったので報告しておきます。(実験医学Vol.27 No.20 アレルギー研究の最前線 高井先生)
ダニの死骸や排泄物はアレルギーの原因として最重要のものの一つですが、それらは単に人に接する機会が多いために、アレルギーの原因なりやすい、というわけではないようです。それらのアレルギー物質はそれ自体、上皮細胞同士の結合組織を破壊し、皮膚のバリア機能を弱める働きがあるようです。さらにそれらは、角化細胞を刺激し、炎症性サイトカインの産生を促すなどし、免疫系をかく乱したり、好酸球を活性化しアレルギーを起こしやすくする働きもあります。
思えば、人の皮膚はありとあらゆる物質と接しており(細菌、真菌、ウイルス、汗、水、食材、花粉、線維、金属、ゴム、クリーム、香料、香水、石鹸、空気、薬剤、塗料など)、その中で、構造上アレルギーの原因となりやすいものがあることは知られていますが、それにはそれなりの理由があると考えたほうがいいかもしれません。その理由はそれぞれの物質によって異なるので、いずれまたご紹介したいと思います。
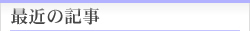

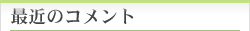

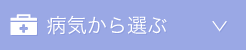
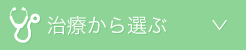
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。