前回のブログで解説させていただきましたが、一度腫れてしまった粉瘤、いわゆる炎症性粉瘤はこれまではかなり時間と手間がかかり、また痛みの伴う治療でした
しかし近年では、手術技術の進歩により、腫れてしまった炎症性粉瘤もくり抜き法を応用したテクニックにより、1回の手術で傷もそこそこ美しく治療する事が可能となりました(1回法)。
この場合は、1回の手術で膿、粉瘤の破片すべて抜き取ってしまいますので痛みや腫れが収まるまでそれほど時間がかかりません。
通常1~2週間で完全に腫れは収まります。
さらに傷も小さくすみます.
これまでのように何度も通院する必要もありません。
あらゆる点で炎症性粉瘤こそ臍抜き法(くり抜き法)にて治療すべきであると考えています。
粉瘤にばい菌が感染し、膿がたまって腫れて痛くなってしまった状態のことを炎症性粉瘤と言います。
現実的には粉瘤が腫れてしまってからクリニックを受診される方がかなり多いです.
しかしこれまでの炎症性粉瘤の治療には様々な問題点がありました。
これまでの炎症性粉瘤の治療は
①まず炎症性粉瘤にメスを入れて膿を抜きます。
②傷口を洗浄し、腫れや痛みが落ち着くまで待ちます。
③腫れが落ちついたら手術を行い、粉瘤を根こそぎ取ってしまいます.
④約1週間後に糸を抜いて治療終了
という流れです.
こう書くとそれほど大変でもないかな、と思う方もおられると思いますが、実際には②の段階で、かなりの苦痛と時間が必要になってきます.
というのも②の段階では粉瘤の破片、粉瘤の内容物などが皮膚の中に残ったままとなっていますので、異物反応を起こし、腫れや痛みがなかなか治まりません。
その結果、延々と抗生物質を飲んだり、病院に通いこととなります.場合によっては毎日のように病院に通い洗浄とデブリドマン(傷口をスプーンのようなものでごしごし削られる)という拷問のような処置を繰り返されることとなります.傷口が落ち着くまで1~2ヶ月くらい治療期間が必要となることもあります.
そして、粉瘤の破片があちこちに飛び散り、またあちこちでへばりついてしまうため(癒着)、③の手術も大規模なものになり、結果的に大きな傷が残ってしまいます.
そもそも粉瘤は必ず取らないといけないのか?と疑問に感じる方もおられると思います.
近くのクリニックで、取らなくても良いと言われた方も多いようです.
結論から言うと絶対に取らないと行けないという訳ではないが、なるべく取っておいた方が良いというのが私の考え方です.
粉瘤は放っておいても生命に影響するものではありません。しかし放っておいて良くなるものでもありません。
粉瘤は年々少しずつ大きくなっていきますし、夏場などには嫌なにおいを発することもしばしばあります.
また粉瘤の中に常在菌が感染してしまった場合、腫れて痛くなり、至急で治療が必要になってしまいます.また一度腫れてしまうと治療が長引いたり、傷がきれいに治らなかったりと行ったトラブルの原因となります.
粉瘤は小さなうちに取っておいた方が手術時間も短くてすみますし、傷もキレイに治ります。
お時間の余裕があれば早めの治療をお勧めしたいと思います。
前回のブログでこれまでの粉瘤治療の問題点について書かせていただきました。
今回は新しい粉瘤治療についての書きたいと思います.
新しい粉瘤治療は小さな穴から粉瘤を抜き取る方法、いわゆる臍(ほぞ)抜き法もしくはくりぬき方と呼ばれている方法です.
この方法では傷が非常小さくなるのですが、技術的にやや熟練が必要で、さらに取り残し、再発の可能性が高くなるとされ、あまり普及してこなかったという歴史がありました。
しかし、傷を小さく治したいという患者様からの要望が強く、徐々に臍抜き法が普及し、現在は臍抜き法の方が標準的となりつつあります.
当院では粉瘤治療年間2332件のうち、大部分を臍抜き法にて治療を行っています。
再発率も通常の方法より劣るものではありません。
粉瘤は皮膚腫瘍であるため、外科的に切除するしかありません。
それは残念ながら今もかわっていません。
粉瘤の手術では、これまで木葉状に皮膚を切開し、粉瘤を取り除き、縫い合わせるという方法が取られておりました。
その場合、例えば3cmの粉瘤を切除するのに、3cm以上(通常ですと6~9cm)の傷が出来るということになります。
この方法は粉瘤の取り残し少なく技術的に容易で誰でもでき再発率が低い反面、大きな傷が残ってしまうという弱点がありました。
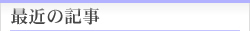

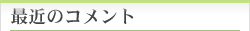

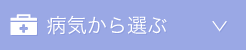
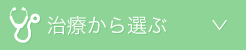
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。