食物アレルギーと一言に行っても少し分類を知っていないと混乱してしまうので少し紹介しておきます
食物アレルギーは食べて数十分以内にアレルギー反応が起こる即時型アレルギーと、食べて数日でアレルギー反応が起こってくる遅発型アレルギーがあります。
また、成長とともに減ってくる食材とそうでない食材があります。
成長とともに食物アレルギーが減ってくる食材・・・卵、牛乳、大豆
成長とともにあまり減ってこない食物アレルギーとは、ピーナッツ、ナッツ類、海老、カニ、魚
さらに、食物アレルギーの原因物質は、完全食物アレルゲンと不完全食物アレルゲンに分類されます。
完全食物アレルゲンとは経口摂取した特殊な蛋白質によって感作が成立し、その後、同じ蛋白質を再度摂取した際にアレルギー反応の誘発に至るもので、卵や牛乳がそれに当たります。それらの食材の中には、熱や消化酵素に対して安定したたんぱく質をもち、とくに小児の未熟な消化管では完全に消化できず、腸管からアレルギーの原因物質となる吸収し感作が成立し、同じ食べ物を食べたときにアレルギー反応が起こるというものです。
それに対して、非完全食物アレルギーとは、すでにある食材に対してほかの経路から感作が成立しており、たまたまその食材を食べたときにアレルギー反応がおこる食材を言います。
非常に有名な例としてラクテックスというゴム製品に含まれる可溶性たんぱく質に対するアレルギーを持つ患者様が栗やバナナ、ソバ、アボガド、メロン、トマト、キウイを食べることでアレルギー反応が出やすいという事実があります。ラクテックスとそれらの食材とには似たたんぱく質の構造があり、ラクテックアレルギーを持つ患者様が、栗やアボガドなどを食べると体内の免疫細胞がそれらのたんぱく質を見つけ、アレルギー反応が出てしまうのです。
先進国でアレルギー疾患が増えている理由について古くから衛生仮説があります。俗に「生活環境が清潔になり過ぎたためアレルギーの病気が増えた」と言われているものです。
簡単にそのメカニズムをご説明します。
体内のT細胞(免疫の司令塔的な細胞)は、感染防御に関与するTh1細胞と、アレルギーを引き起こすTh2細胞のどちらかに分化します。それらは互いに抑制しあい、バランスをとっていますが、清潔にし過ぎると感染源と接触する機会が減り、Th1が弱まり、Th1とTh2のバランスがTh2に偏ってしまった結果、アレルギー疾患が増えたのではないか?とする説です。
なるほど、と思われるかもしれませんが、もしそうならばTh1優位になると発症してくる自己免疫疾患は先進国では減ってくるはずなのですが、実際にはそれらの病気も先進国で増えているとのデータがあり、すべてTh1/Th2バランスで説明することは困難なようです。
しかし、ある時期、おそらく幼少期に、原始的な生活と比較しTh2優位になる傾向があり、その時期に大気の乾燥や、体の擦り過ぎなどが加わって、角質がカサカサになり、その本来の防御力が低下し、外からのアレルギー物質の通過を許すようになれば、実際にアレルギーになりやすくなるのではないかと私は思うのです。以前のブログで何度かふれたとおり、腸管からではなく皮膚からアレルギー物質を通過させることでアレルギーが始まることが多いことがわかってきています。
ある程度、衛生面で清潔になったことはもちろん悪いことではなく、乳児の死亡率が激減させるなど良いことのほうが多いと思いますので、今更、原始的な衛生環境に乳児を置くなど、全くもって現実的ではありません。そのかわりに、なるべく体を擦り過ぎない、部屋を乾燥させすぎない、保湿剤をきちんとつけてあげるなど、アレルギーを防ぐためにできることを地道にやるのがいいのではないかと考えています。
花粉症皮膚炎という病気があります。なんとなく聞いたことがあるような名前ですが、その疾患概念が確立したのは比較的最近のことです。
通常、花粉症といいますと、目や鼻などの粘膜に花粉が付着し、IgEを介して肥満細胞からヒスタミンが分泌されるいわゆる即時型アレルギーのことを言います。
一方、花粉症皮膚炎とは、まさに花粉が皮膚につくことによってかゆみや湿疹が起こり、特にアトピー性皮膚炎の方は症状が増悪します。IgEが関与するいわゆる接触性蕁麻疹の場合(即時型アレルギー)と、感作されたT細胞が関与するアレルギー性接触皮膚炎の場合(遅延型アレルギー)の場合があります。
花粉の季節に皮膚のかゆみが出る方、アトピー性皮膚炎が増悪する方は、花粉症皮膚炎の可能性があります。なるべく皮膚を露出しない、家に帰ればすぐにシャワーを浴びるといった対策が有効です。
少し飛んでいる花粉についてまとめておきます(関東の場合)
スギ:1月下旬~5月上旬
ハンノキ:1月中旬~6月上旬
ケヤキ:3月中旬~6月上旬
ヒノキ:3月下旬~5月中旬
コナラ:3月下旬~6月中旬
クリ:3月下旬~6月中旬
ミズナラ:3月下旬~6月中旬
イチョウ:4月
ポプラ:4月
ヤナギ:4月
マツ:4月上旬~6月下旬
シラカンバ:4月中旬~5月下旬
ギシギシ;4月中旬~6月中旬
クマシデ:4月下旬~6月中旬
カモガヤ:5月上旬~6月下旬
イラクサ:8月上旬~10月上旬
ブタクサ:8月下旬~9月下旬
オオヨモギ:8月下旬~10月中旬
ヨモギ:9月上旬~10月下旬
カナムグラ:9月~10月中旬
そろそろ花粉が気になる季節になりました。
花粉症の方は、早めに治療をしたほうが軽症で済みますので、気になる方はご相談いただければと存じます。
湿疹の症状というと、皮膚がカサカサしていて(鱗屑)、赤みがあり(紅斑)、赤いポチポチがあり(紅色丘疹)、ときに皮膚がごわごわしている(苔癬化)というイメージですが、時に見た目では何にもなくても、「湿疹」として考えたほうがいいことがあります。
それが病理学的湿疹と呼ばれる考え方で、「湿疹に至る少し前」というイメージでいいとか思います。見た目では何にもなくとも、顕微鏡で調べるとリンパ球などの炎症細胞が真皮上層に集まってきている状態です。通常痒みを伴います。
その状態になってしまったら、遅かれ早かれ通常の湿疹に至ってしまうため、速やかにステロイド外用、もしくはプロトピック外用を導入し、早期に治療したほうがいいのではないかという考え方があります。
これまでは、視診上、特に問題のない皮膚にステロイドやプロトピックを付けることは抵抗があったのですが、病理学的湿疹という概念が出てきてからは抵抗が少なくなりました。
ただし、どのように病理学的湿疹と診断すればいいかという問題があります。全員に皮膚生検することなど現実的には不可能ですし、病理結果が出るころにはすでに早期治療が効果を表すゴールデンタイムは過ぎていると思われます。
痒みのある方全員に病理学的湿疹かもしれないと、ステロイドをご処方するのは過剰です。(何度かブログでご紹介したとおり、痒みは炎症によるものとは限らず、ステロイド外用が無効であることもしばしばあるためです)。
やはり、予防的に保湿剤を付けていてもステロイドすぐに湿疹が再発してしまう慢性湿疹の患者様、標準的な治療をしているのに何度も再発を繰り返しているアトピー性皮膚炎の患者様に限られるかと思います。
この概念、治療のいいところは、ほぼ見た目には湿疹のない状態がキープできる点で、患者様も良くなっていると実感しやすい点です。さらに、この治療のいい点は、湿疹のない状態がキープできればできるほど、ステロイド外用薬に対する反応は鋭くなり、結果的に使うステロイドの強さを弱くしたり、少なくすることができる点です。
病理学的湿疹という考え方を有効に利用することは、湿疹やアトピー性皮膚炎の患者様を治療するうえで優れた武器になります。
昨日は、地域の医師会の会合があり、僭越ながら、アトピー性皮膚炎についてプレゼンテーションさせていただきました。
アトピー性皮膚炎の発症機序についての考察、治療法などについて述べさせていただきました。地元の有名な先生方が多数おられる前での発表でしたので、少し緊張しましたが、貴重な経験ができたと感じています。
皮膚科の先生は来られていないと思い、専門的な話は避けたのですが、後で皮膚科の先生も来られていたことがわかり、少し冷や汗をかきましたが。
その後、懇親会でお酒を交え、他科の先生方と交流することができ、楽しく過ごすことができました。
やはり他科の先生とのネットワークがあるのは心強く感じます。
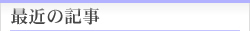

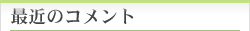

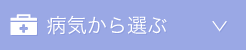
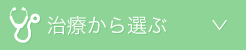
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。