帯状疱疹の患者様が増えている印象があります。
帯状疱疹は神経節に潜伏感染しているVZV(水ぼうそうウイルス)が再活性化することによって発症します。
VZVは数年から数十年以上にわたり免疫学的監視下に置かれ、潜伏感染を続けます。何らかのきっかけで監視が弱まること(たとえば、過労、ストレス、悪性腫瘍、重症感染症など)により、VZVが再活性すると帯状疱疹が発症します。
再活性化されたウイルスは神経細胞を伝わり、毛包細胞や表皮細胞に到達します。そうなれば皮膚に紅斑や水疱が形成されます。
このまま放置すれば、表皮から真皮に感染が波及し、さらに血管内皮細胞にも感染し、局所での循環障害を引き起こします。そうなれば皮膚は潰瘍化し、治療が長引いてしまいます。(二次感染により潰瘍化していると考える方もおられますが、それだけではなく、上記のような機序があります。二次感染だけにしては、やけに深い皮膚潰瘍が形成されるのが特徴です。)
さらに帯状疱疹は治癒しても、疼痛が長引くことがあります。帯状疱疹後神経痛と呼ばれ、ご高齢の方ほどそのリスクは高いとされています。
その痛みは通常の痛みと異なります。通常の痛みは神経は正常で、痛み神経の受容器が刺激を受けることで痛みとして自覚しますが、帯状疱疹後神経痛の場合は、神経自体が損傷を受けているため、神経が異常興奮することにより発症します。
そのため、帯状疱疹後神経痛には通常の痛みどめは効きにくく、特殊な薬によって治療していくことになります。
なるべくそうならないように早期の受診、治療が望ましいと考えています。痛みとその部位における皮膚の水疱、紅斑を見つけた場合は、出来ればすぐに皮膚科に受診するようにしてください。
今月の日本皮膚科学会誌を読んでいたところ、慢性創傷で創が治りきらない場合の注意点について列挙されていたので紹介させていただきます。(創傷治癒の基礎 群馬大学 石川治先生)
英語の頭文字をとって、TIMEの概念といわれているそうです。
1 壊死組織の残存
2 感染および炎症
3 創の乾燥あるいは創周囲の浸軟(ふやけていること)
4 創辺縁の上皮化の遅延または下掘れ
1,2はご存知の方が多いと思われますが、壊死物質がついていたり、感染があると創は治りません。
3に関しては、創は湿潤環境(湿った状態)で治すの標準的となっていますが、創からの浸出液が多く、創周囲がふやけてしまうほどになれば、逆に傷の治りが悪くなるということです。ただ単に湿っているだけでは十分とは言えないと言い換えられるかと思います。
4に関しては、創の辺縁が治らずに、辺縁から軒先状に皮膚が張り出してきて時にポケットを形成することがあります。そうなるといくら治療しても創は治らないので、ポケットを切除する必要があります。(下手な日本語で失礼しました。)
手湿疹は多くの場合、水仕事を長く行う方に出来やすく、洗剤などで手の皮脂膜や角質の保湿成分が洗い流されることで、皮膚のバリア機能が低下することにより発症します。
また、美容師さんなど化学薬品をたくさん扱う方の場合は、薬品にかぶれて手湿疹を発症することがあります。
しかし中には「水仕事はしない」、「化学薬品を扱わない」のに、手湿疹を発症し、なかなか治らない方もおられます。その場合の考えられる原因については以下の物質についてのかぶれが疑われます。
ニッケル(ドアノブ、はさみ、調理器具、髪留めなどに使われています。)
重クロム酸カリウム(セメント、革製品などに使われていましたが、最近はあまり使われていないとのこと。)
ゴム(ゴム手袋、ホース、ベルト、コードなどに使われています。)
香料(化粧品、石鹸、市販の塗り薬などに使われています。)
ホルムアルデヒド(接着剤、防腐剤、建築機材などに使われています。)
ラノリン(皮膚のクリーム、潤滑剤、プラスチックなどに使われています。)
頻度的にはそれほど多くはないのですが、難治性の手湿疹で原因がはっきりしない場合は上記の物質などでかぶれている可能性を考え、検査をし原因を追究していったほうがいいと考えています。
外来中、患者様には「皮膚を掻かないでください、擦らないでください」とよくご説明させていただいておりますが、その理論的根拠を少し述べたいと思います。
まず掻くことにより角質層が痛み、アレルゲン(アレルギーの原因物質)、微生物の通過を許してしまうことが一つあげられます。それについては何度か書いたことがあるので、今回は割愛させていただきます。
そのほかにも、掻くことで表皮細胞が傷害され、サイトカインと呼ばれる伝達物質が放出されます。サイトカインによってさまざまな免疫細胞が寄ってきて炎症が起こり、皮膚炎が増悪してしまいます。
そのほかにも、掻くことにより、末梢神経の求心性C線維と呼ばれる部位からサブスタンスPと呼ばれる物質が放出され、マスト細胞に作用し、ヒスタミンが分泌されます。その結果かゆみが増してしまいます。さらにサブスタンスPは血管拡張作用、血管透過性亢進作用もあり、炎症を悪化させてしまいます。
それが、よく言われている「掻くことにより痒みが悪化する」ことの病態を表していると思います。
どうしてもかゆいときは、掻かずに、保冷材などで30秒ほど冷やしていただきたいと思います。そうすればたいていのかゆみは一時的に収まると思います。
余談になりますが最近、サブスタンスPはストレスにより放出されやすくなるのではないか?といわれるようになりました。それが正しいとすると、「ストレスにより、掻く行動が助長され、結果的に皮膚炎を増悪させる」ことの病態の理解につながります。(もちろんストレスが皮膚に与える影響は、ホルモンの変化など様々な角度から分析しなければならないのですが)。
本日はかぶれ療法について少し述べたいと思います。
かぶれ療法とは人工的にかぶれを起こすことにより、疾患の治癒を促す方法です。「皮膚科医はかぶれを治すのが仕事ではないか?」と訝しがられることがあるのですが、うまく使えば、かなり優れた治療効果が得られます。
かぶれ療法を行うのは
尋常性疣贅(いぼ)
円形脱毛症
の二つです。
いぼのかぶれ療法については以前、SADBE療法の項で述べたのですが、要約すると、かぶれを起こすことで、免疫細胞をいぼの周囲にたくさん寄ってこさせ、いぼウイルスを駆除させる、ということになります。
では円形脱毛症にはどのように作用するのでしょうか?
円形脱毛症は、自身の免疫細胞が、毛根を攻撃することにより発症すると考えられていますが、そこにかぶれを起こすことで、さらにたくさん免疫細胞が寄ってきます。
免疫反応が起これば、その免疫細胞の中に、制御性T細胞(Treg)もたくさん含まれており、いずれ免疫反応を鎮静化させてくれます。その際に、毛根を攻撃していた免疫細胞も同時に鎮静化させているのではないか?と考えられています。
ちなみにCinical dermatology fifth editionという米国の教科書には、かぶれ療法は、難治性の円形脱毛症に対しては、最も有効な治療法と記載されております。日本では保険適応でないのが残念なのですが、当院では保険適応の治療でどうしても反応しない患者様においては、かぶれ療法を行うことができます。(かぶれ物質は無料で提供させていただきます)。
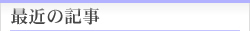

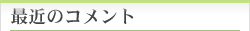

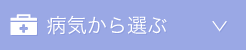
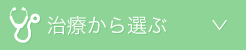
※掲載内容・料金は更新時点での情報の場合がございます。最新の内容、料金は各院へお問合せください。